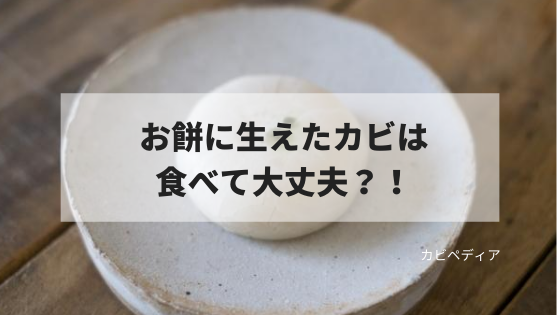
お正月に買った餅がたくさん余ってしまうという家庭も多いですよね。
しかし時間が経つと、表面に白い粉のようなものが出たり、緑や黒のカビが付いてしまうこともあります。
「カビが少しだけなら、そこを取れば食べられるのでは?」と思う人もいますが、それは非常に危険です。
餅に生えるカビの多くは、人体に有害なカビ毒(マイコトキシン)を生成する可能性があり、加熱や冷凍では完全に無毒化できません。
この記事では、餅にカビが生える原因や代表的なカビの種類、そしてカビの生えた餅を食べてはいけない理由を専門家の視点で解説します。
さらに、カビを防ぐための正しい保存方法や、家庭でできるカビ予防のポイントも紹介します。
家族や自身の健康を守り、餅を美味しく食べるために正しい知識を身につけましょう!
| この記事でわかること |
| ・餅にカビが生える理由やカビの種類 ・カビが生えた餅の危険性 ・餅にカビを発生させないための保存方法 |
目次
1.餅にカビが生える理由

まずは何故餅にカビが生えてしまうのか、その理由から見ていきましょう。
餅にカビが発生する条件は、家庭でカビが生える条件は同じで、以下の4つが揃っている必要があります。
- 水分(高湿度)
- 暖かい温度
- 栄養素
- 酸素
餅は、デンプン(炭水化物)や水分、脂質などを含んでいるため、それだけでカビの発生条件の水分と栄養素が揃っています。
また、正月は冬なので外気の温度は低いですが、室内は暖房などで温度が高くなりやすく、特にキッチンやリビング付近は暖かくなりやすいでしょう。
もちろん人間が生活する場所には酸素は必ずあるので、これでカビの発生条件の4つが揃ってしまうのです。
食品のカビが気になるなら、まずはカビリスク診断
餅のカビは保存方法が大前提ですが、住まいの湿気環境によって食品がカビやすくなることもあります。
カビリスク診断でご自宅がどれくらいカビを招きやすい環境か、一度チェックしてみてください。
2.餅に生えるカビの種類
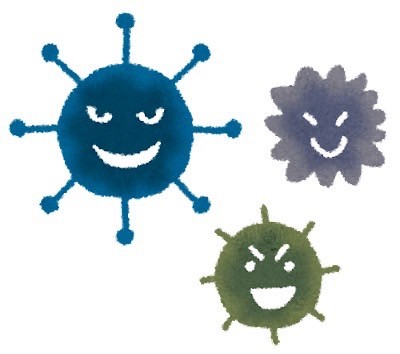
では、餅に生えやすいカビの種類についていくつか挙げていきたいと思います。
2-1.青カビ
ペニシリウム属のカビで、みかんなどの柑橘類などにも生えやすいカビです。
青カビの難しさは有害なものと無害なものがあるところです。無害なものはチーズなどにも利用されますが、有害なものの中は「マイコトキシン」という強い毒性のあるものもあります。
また、青カビは呼吸器系のカビアレルギーの原因になるものもあるので、「青カビだから大丈夫」とは言えないのです。
2-2.赤カビ
加湿器や洗面所、お風呂などで生えやすいカビです。これはロドトルラという酵母菌の一種です。
根を張って繁殖するカビではありませんが、繁殖スピードが非常に早いという特徴があります。また、赤カビが生えると黒カビも発生しやすくなるため、注意が必要です。
赤カビにもマイコトキシンというカビ毒を持つものが多く、特にマイコトキシンの中には猛毒のアフラトキシンもあるので、赤いカビが生えた餅は絶対に食べないようにしましょう。
参考:厚生労働省「カビ毒評価書」
2-3.黒カビ
室内でも発生しやすいカビの一種です。
色素が残りやすく、生命力も非常に強いという特徴があります。
一度根を生やすと見えない部分にも菌糸を広げている可能性があります。これが「カビが生えている部分だけを削って食べても危険」と言われる理由です。
また、黒カビはハウスダストの原因になると言われています。
3.Q&A「〇〇なら、カビが生えた餅を食べてもいいの?」

餅にカビが生えた時に、「カビの部分だけ取り除けば食べられる」「加熱したら菌が死ぬから食べられる」などと言う方がいます。
実際、本当に食べても大丈夫なのでしょうか?
ここでは、よくある質問をまとめてみました。
Q1.カビが生えていない部分は食べても良いの?
黒カビの話でも書きましたが、カビは実際に見えていない部分でも「菌糸」を張って繁殖しようとしています。
そのためカビが生えた餅は、いくら表面のカビ部分をカットしても、目には見えないカビを摂取している可能性が高いです。
アレルギーやカビ毒による食中毒を防ぐためにも、一度カビが生えた餅は食べないようにした方が安全でしょう。
Q2.餅のカビは加熱したり冷凍すれば無毒化するの?

一度生えてしまったカビのカビ毒は、加熱をしても、冷凍しても無毒化しません。
そのため、「焼いたらカビは死滅するから大丈夫」とカビが生えた餅を加熱して食べないようにしましょう。
今は大丈夫でも、マイコトキシンによってカビ毒が少しずつ蓄積して、将来ガンを引き起こす…という危険も考えられます。
(参考:農林水産省「餅に生えたかび」)
Q3.餅にカビが生えてもカビ臭がしなかったら大丈夫?
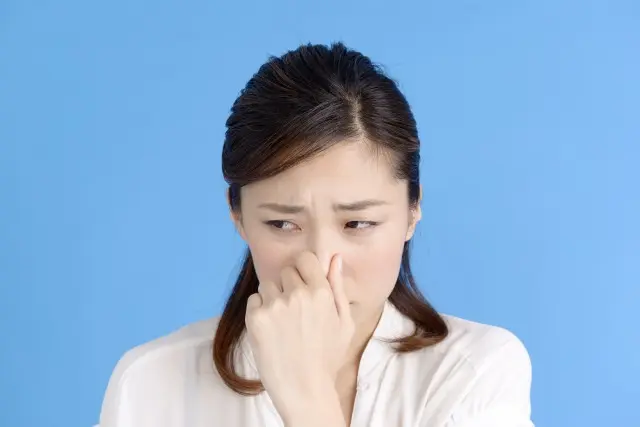
カビには特有の「カビ臭さ」というものがありますが、たまにカビの臭いがしないケースもあります。
もちろん、カビが生えた餅からカビの臭いがしなければ食べて良いというわけではありません。
カビにも色んな種類があり、中にはカビ臭くないものもあります。少しでも餅の表面にカビが生えていたら、全くカビ臭くなかったとしても食べない方が良いでしょう。
Q4.餅に生えたカビは水で洗えば大丈夫?
カビは一度生えたら見えない部分にも根を生やしてしまっている可能性があります。また胞子を飛ばしている可能性もあります。
水で餅の表面を洗ってカビを洗い流したとしても、カビは生き残ります。
「カビた餅を水で洗ったから食べられる」と思っている方もいるようですが、カビ毒による食中毒や発がんの原因になるので食べないようにしましょう。
4.つまり、カビの生えた餅は食べない一択!

これまでの内容をまとめると
「カビが生えた餅は、有害か無害かは見分けがつかないから食べない方が良い」
ということになります。
少量食べて今は大丈夫だったとしても、少しずつ影響を受けている可能性もあります。
そして一番大事なことは、そもそも餅にカビを生やさないことなのです。
餅に生えたカビが有害なのか無害なのか肉眼で判断するのは難しいですし、加熱しても冷凍しても一度生えてしまったカビは無毒化することはできません。
だからこそ、最初から餅にカビが生えないようにしっかりと対策しなければいけないのです。
5.餅にカビを生さない保存方法

続いて、餅にカビを生やさない保存方法について紹介します。
とはいえ、ここで紹介する方法で完全にカビを防げるわけではないですし、期間にも限界はあるので、まずは餅を「買い過ぎない」「貰い過ぎない」「作り過ぎない」ように心がけてください。
それでも一定期間保存しなければいけない時に、これから紹介する方法で保存しましょう。
5-1.湿度の低い場所に保存
カビが発生する上で特に影響を与えてくるのが、水分や湿気です。
温度や湿度が上がりやすいキッチンやリビングの周りではなく、乾燥している倉庫などに保存するというのも1つの方法です。
ただし、湿度や温度の管理を徹底しないとカビは発生してしまいますので、油断は禁物です。
5-2.冷凍保存
もっとも手っ取り早い餅の保存方法は冷凍することです。
カビが生えてから冷凍しても無毒化しないですが、カビが発生する前に冷凍するならカビが生えるのを防ぐことができます。
お正月の時期は冷凍庫がパンパンになっているというご家庭もあるかと思いますが、長期間食べない餅はできるだけ冷凍庫に入れるようにしましょう。
冷凍庫を開け閉めした際に霜が付いたり、劣化する可能性もあるので、冷凍した餅は2~3週間くらいを目安にして食べきるようにしましょう。
5-3.殺菌効果のあるワサビや唐辛子と保存
殺菌力のあるワサビや辛子、唐辛子などと一緒に餅を保存するという方法です。
短期間の保存では効果が期待できますが、こちらはあまり過信しすぎない方が良いでしょう。
チューブワサビを紙にくるんで餅と保存するというやり方でもいいですが、米びつ用のわさびや唐辛子と一緒に保存というのもおススメです。
6.餅にカビが生えやすい家=至る所にカビの胞子がいるかも!?

そもそも餅にカビが生えやすいということは、その家自体にカビが発生しやすくなっているかもしれません。
カビの胞子は常に浮遊しているもので、カビが生育しやすい環境を見つけるとそこで繁殖します。
そしてカビの胞子の量はご家庭によって様々です。
すでに自宅内にカビが発生していると、空気中のカビの胞子が多くなり、餅にカビが生えやすくなります。
そのような環境では、餅だけでなく、壁や家具、洋服などにもカビの被害が発生してしまうかもしれません。
もしすでにご自宅にカビが発生しているなら、すぐに除去しましょう。

カビ取り業者のハーツクリーンが開発したカビ取りマイスターキットなら、危険な成分が含まれていないため、壁や家具、押入れなどのカビ取りにも使用できます。
また、実際に業者が使用している液剤を誰でも使えるように改良した商品なので、自宅でプロレベルのカビ取りができます。
防カビ剤もセットなので、カビの再発も防げます。
徹底的にカビ取りしたい場合は是非検討してみてください。

もしまだカビが生えていないようなら、しっかりと換気や掃除をしてカビを防ぎましょう。
カビはアルコールに弱い性質のため、消毒用エタノールを使って除菌してください。
これで目に見えないカビの胞子を死滅させることができます。

ドーバー パストリーゼ77
出典:Amazon

フマキラー キッチン用 アルコール除菌スプレー
出典:楽天市場
また、空気清浄機を使用すると、空気中のカビの胞子や埃を除去してくれるので、部屋にカビが生えにくくなります。
7.まとめ
餅にカビが生えると、「勿体ないからカビが生えていない部分だけでも食べられないかな…?」と思う方もいると思いますが、カビが生えた食品を口にするとカビ毒による食中毒や発がんの原因になるかもしれません。
そのためカビが生えた餅は食べないようにするのが一番です。
また、毎年のように餅にカビが生えたりしているようなら、保管場所や家全体にカビが発生しやすくなっている可能性があります。
心配ならカビ取りのプロに相談して、根本的にカビを除去してもらいましょう。

■関連記事■そうめんに生えたカビは食べても大丈夫?!
■関連記事■野菜に生えたカビは食べても大丈夫?!
■関連記事■【Q&A】クリームチーズに生えたピンク色のカビは食べられる?
■関連記事■カボチャのカビは食べても大丈夫?カビの種類や正しい保存方法は?
■関連記事■カビの生えたさつまいもは食べても大丈夫?!正しい保存方法は?!
■関連記事■カビの生えたオレンジは食べても大丈夫?!
■関連記事■パンに生えたカビは食べても大丈夫?!







コメント