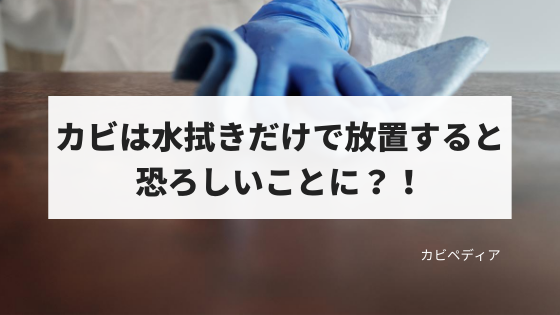
家の中でカビを見つけたとき、「とりあえず水拭きでいいかな…」と掃除していませんか?
実はその方法、間違ったカビ取り方法の中でも特に多い事例のひとつです。当社がカビでお困りのお宅へ伺った際に目にする『カビを悪化させる間違った掃除方法ランキング』では、最も危険なのが「掃除機で吸う」、次に「乾拭きをする」、そして「水拭きをする」と続きます。
水拭きだけでは、カビをきれいに落とせないどころか、逆に水分によってカビに栄養を与え、繁殖を助けてしまう恐れがあります。
この記事では、水拭きがカビ取りに不十分な理由を詳しく解説するとともに、カビの状態に合わせた正しい除去方法をご紹介します。さらに、プロの視点から「カビを再発させないためのポイント」も徹底解説!
正しい知識を身につけて、カビに悩まない快適な環境づくりにお役立てください。
| この記事で分かること |
| ・カビ掃除に水拭きがNGな理由 ・カビの状態別に見る除去方法 ・カビを予防する方法 |
目次
1.カビ掃除は水拭きはお勧めしない理由

先ほど説明したようにカビ掃除は水拭きはお勧めしません。水拭きすることでカビが成長するのに必要な水分を与えてしまい、青カビ白カビは、瞬間的には綺麗になりますが、中期的に見るとカビをさらに発生させてしまう恐れがあるのです。
1-1.カビは水分が大好き
たとえば、「家の中で一番カビが発生しやすい場所はどこでしょうか?」と聞かれると、多くの方は「お風呂場」と答えるかと思います。お風呂場は高温多湿で水分が残りやすく、カビにとって好条件だからです。
実は、「水拭き掃除」もこれと似た状況を作り出してしまいます。特に、青カビや白カビは一見ホコリと間違えやすく、水拭きで掃除しがちですが、これらのカビは布製品や木製建具など栄養素が豊富な場所に発生することが多いため、水拭きをするとかえってカビに水分と栄養を与えてしまいます。
つまり、水拭きだけではカビの成長を促進させ、増殖したカビがカビ毒や胞子を多く発生させることで、カビ被害がさらに広範囲に広がるだけでなく、健康被害のリスクも高めてしまう恐れがあります。
1-2.特に畳は要注意

布や木などもカビが発生しやすいですが、特に中が必要なのは畳になります。畳は湿気を吸いやすいので特に要注意です。水拭きはもちろん、乾拭きや叩くこともNG。そうすると畳の中にカビを入りこませてしまいます。最も確実なのは、塩素系漂白剤を浸した綺麗な雑巾でしっかりと除菌します。菌を除菌した後に液剤成分を残さないように水ぶきを行い、送風機を使って乾燥させることをおすすめします。
また、畳に発生するカビはアスペルギルスなどの青カビが多く、アスペルギルス性肺炎など重篤な病気の元になるため、カビ取り時にはカビ胞子を吸い込まないよう、マスクを着用し換気をしっかりと行いましょう。
■関連記事■新築の畳はカビやすいって本当!?畳の青カビを簡単に除去する方法と再発予防策を解説
カビが繰り返すなら、まずはカビリスク診断
カビを除去して一時的にきれいになっても、住まいの湿気環境が強いと同じ場所に再発しやすくなります。
カビリスク診断でご自宅がどれくらいカビを招きやすい環境か、一度チェックしてみてください。
2.生えてしまったカビを除去する方法
それでは、汚れの種類別に生えてしまったカビ取りをする方法を説明していきます。
2-1.軽いカビ汚れの場合
軽いカビ(カビがうっすら生えている状態)の場合、エタノールスプレーを吹きつけ除菌をおこなった後に、綺麗な雑巾を水で浸し、固くしぼったクロスで表面を吹き上げます。表面が乾いたら、仕上げに再度エタノールスプレーを吹きつけ除菌します。エタノールは薬局などで売られている80%濃度の「消毒用」が最も効果が高いのでお勧めしています。
その他、軽度のカビでカビの色素が沈着していない程度でしたら逆性石けんや次亜塩素酸水、重曹などを使って除カビすることもできます。

ドーバー パストリーゼ77
出典:Amazon
■関連記事■エタノールでカビを撃退!アルコールの殺菌効果と正しい選び方
2-2.中度以上のカビ取りの場合
中度以上(しっかりとカビが見えている状態)のカビの場合からは、カビ取り剤を利用することをお勧めしています。汚れが強いときには、カビ取り剤をかけた後にラップで密封し、少しつけおきすることで、より効果的にカビを落とすことができます。カビの上に汚れが付着している場合は、下記で紹介するような中性石鹸で汚れをとってからカビ取り剤を噴霧すると、カビを確実に除去することができます。

東邦 ウタマロクリーナー
出典:Amazon
また、カビ取り剤については、市販薬でよく使われている水酸化ナトリウムが添加されていない、当社オリジナルの液剤をお勧めしています。こちらは乾燥すると食塩になるよう設計して作っていますので、安心してご利用いただけます。

カビ取り剤を使うときに注意する点は
・マスクとゴーグルを着用する
・窓をあけて換気する
・ゴム手袋を着用し、カビ取り剤が肌にふれないようにする
・肌についてしまった場合は流水で十分にすすぎ落とす
・酸性タイプの洗剤とは絶対に混ぜない(塩素ガスが発生するため)
となります。よく注意してつかいましょう。
以上がカビが生えてしまったときの対処法です。自力で除カビをしてもカビが再発してしまう場合には、素材の奥にカビが菌糸を伸ばして発生している場合があります。例えば、カビの上から塗装を重ねてしまった塗装壁などは塗装を剥がさなければ、上から何度もカビを除去しても再発してしまいます。
このような場合ですと、カビ取り業者に依頼し、塗装を剥がして除カビしなければカビの再発を繰り返します。
■関連記事■キッチンの黒カビ対策決定版|シンクの素材別カビ取りと再発防止策【ステンレス・大理石・ホーロー】策
■関連記事■お風呂の天井のカビは危険!10倍速く増殖する理由と最強のカビ取り方法
2-3.プロの液剤で再発を防ぎたい場合

水回り以外では、水酸化ナトリウムが添加されている市販の塩素系カビ取り剤は使用できません。そこでお勧めしているのが、当社が独自に開発した液剤になります。
こちらは、実際の職人が使う液剤と同じ成分でできており、先ほど紹介したカビ取り剤に防カビ材がセットになっていますので、カビの再発防止にお役立ていただけます。

3.カビを発生させない環境づくり
頑張ってカビを除去できたとしても、カビが発生しやすい環境であれば再びカビが生えてしまいます。ここでは再びカビを発生させない方法についてみていきます。
3-1.換気をこまめにしよう
現在の住宅は高性能になった断熱材により高気密、高断熱を実現しています。これにより夏はクーラーで冷えた空気を、冬は暖かい空気を持続させられるようになり、省エネにつながっています。しかし一方、外気と中の空気との温度差により結露が発生しやすくなっています。

(結露もカビの原因↑)
これはカビにとって好環境といえるでしょう。よってカビ対策のためには「換気」をしっかりとすることが重要となります。
・24時間換気扇をつけっぱなし
・朝や夕方に窓をあけて空気の入れ替え
・室内の整理整頓(空気の通り道を生成)
まずはこれらのことを見直してみましょう。
■関連記事■結露によるカビ発生を防ぐ方法とは?湿気対策の基本と予防策7選
3-2.温度・湿度管理を意識しよう

またカビが発生しやすい条件に「湿度60%以上」「温度20〜30℃」というものがあります。これへの対策とし「温度・湿度管理」が重要となります。
・室内干しをしない
・必要以上に暖房の温度を上げない
・必要以上に加湿しない
まずはこれらを徹底してみてください。
もしどうしても室内干しをしなければいけない時は、除湿機を活用するのもいいです。
また、普段から部屋の温度や湿度をチェックしておくのもおススメです。除湿器を使うタイミングや換気を意識しやすくなります。
■関連記事■カビ臭・生乾き臭を防ぐ!部屋干しの正しいやり方と除湿・換気のコツ

シャープ 衣類乾燥機除湿機 プラズマクラスター
出典: Amazon

タニタ 温湿度計
出典:Amazon
3-3.こまめに掃除しよう

カビが発生しやすくなるためのもう1つの条件が「栄養源があること」です。カビは食品や食べこぼしはもちろんのこと、塵やホコリも栄養源にすることができます。
・掃除機をかける
・モップ掛けをする
・空気清浄機を使う
などの方法で室内の環境をよいものにしましょう。
また、エアコンの掃除についても注意が必要です。内部にカビが発生してしまうと、エアコンをつかうたびにカビの胞子が空気中に舞ってしまいます。普段からフィルターのこまめなそうじをすることと、内部乾燥機能をつかってカビの発生を防ぎましょう。
■関連記事■【保存版】久しぶりに使ったらカビ臭い!?エアコンの結露・簡単掃除・予防法まとめ
3-4.不用品は処分しよう
床にモノをたくさん直置きしていると、湿気がたまりカビの原因となります。
使っていないものは処分したり、直置きのものは収納ケースやかける収納をするなどして通気性を良くしましょう。
また、あまり使わない部屋であっても、こまめに換気をして、空気を循環させることがカビ予防になります。
■関連記事■カビが生えにくい部屋作りのコツ|家具配置とインテリア選びで湿気対策を!

3-5.布団やカーペットの敷きっぱなしに注意しよう
寝具やカーペットをを床に敷きっぱなしにしていると湿気が溜まりカビの原因となります。カビが生えてしまうと、そのまま普段のお掃除のように水拭きをしてしまいがちですが、一度カビが生えてしまうとちゃんと殺菌をしないとカビが再発する恐れがあります。
そのため、寝具やカーペット類はこまめに上げて床掃除をしたり、天日干しをして湿気を除去しましょう。窓の内部屋の場合には、除湿機やサーキュレーターを使って除湿してください。
4.【カビ最新ニュース】住宅内のカビは「喘息の新規発症リスク」とも関連する可能性
近年のメタ解析(複数研究の統合解析)では、子どもの頃に「家の中にカビがある環境」で暮らすことが、将来、喘息を発症するリスクが高まる可能性があることが示されました。
カビは目に見える前から広がり、拭き取ったつもりでも菌や胞子が残りやすいうえ、水拭きによって湿気が加わることで、かえって再発しやすい環境を招いてしまいます。
だからこそ、カビを見つけたら「水分を足さない」「殺菌する」「最後にしっかり乾かす」という順序で対処をすることが重要です。
参考:Childhood asthma and mould in homes—A meta-analysis
5.カビ取りに関するQ&A
カビは「見える部分だけ落とす」では再発しやすいので、手順と判断基準を押さえておくと安心です。
Q1. 水拭きはダメでも、拭き取り自体は必要では?
必要です。
ただし順番が重要で、基本は「殺菌(エタノール等)→拭き取り→乾燥」です。
水を足す作業をする場合も、最後に必ず乾拭きと送風で水分を残さないようにします。
Q2. どの薬剤を選べばいい?
軽度の白カビや、カビ臭い程度なら消毒用エタノールで対応できることがあります。
黒ずみが見られたり広がっている場合には、塩素系や専用のカビ取り剤など、素材に適した薬剤を選ぶことが重要です。特に木材や畳、壁紙は扱いに注意が必要です。
Q3. 自力でやめて業者に相談すべきサインは?
同じ場所で何度も再発する、壁紙の裏や床下など見えない場所が疑わしい、広範囲に広がっている、カビ臭が取れない、咳や喘鳴などの体調不良が出る場合は早めに相談がおすすめです。
6.まとめ
- カビは水分を好むため水拭きだけではかえって逆効果
- カビ再発の恐れがある
- そのためには、専用のカビ取り剤や消毒用アルコールなどを使ってしっかりと殺菌し乾燥させることが重要
- 軽度のカビであれば、中性洗剤でも除去できるが場所とカビの程度による
- 自分でカビ取りしてもカビが再発する場合には、素材の奥からカビが菌糸を伸ばしている可能性があるのでカビ取り業者に相談する
カビは拭いただけで除去できるような生易しいものではなく、一度生えてしまうと対処が面倒な代物です。しかも、そのまま放っておくと健康に害が及ぶことも。普段からカビが生えさせない予防が大切になりますので、上記の方法を実践し、カビを発生させない環境づくりを心掛けましょう。
また、一度カビが発生してしまう家は見えない部分にも多くのカビの胞子が飛び散っている可能性もあります。掃除をしても何度も何度もカビが再発する場合には一度、カビ取りの専門業者に相談してみてはいかがでしょうか。







