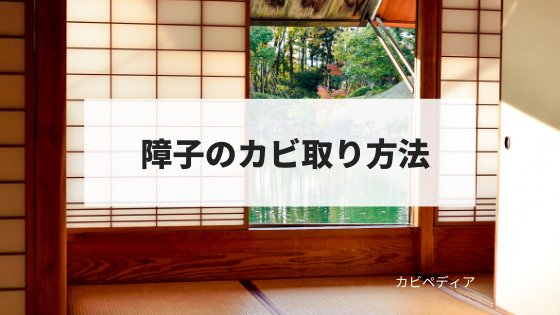
通気性や調湿性に優れ、和室の雰囲気を引き立ててくれる障子。
しかし実は、結露や室内の湿気によってカビが発生しやすいということをご存じでしょうか?
私たちがカビの調査を行う際にも、障子や掛け軸などの「和紙部分」は、カビの繁殖状況を確認する重要なチェックポイントのひとつです。
障子にカビが生えると見た目が悪くなるだけでなく、部屋全体へ胞子が飛散してカビを広げる原因にもなります。
特に多いのが「青カビ(アオカビ)系」で、空気中に拡散しやすく、健康リスクにも注意が必要です。
この記事では、障子にカビが生える原因から、障子紙や木枠についたカビの落とし方、再発を防ぐための予防策まで、わかりやすく解説します。
また、カビに強い障子紙の選び方や、日常的なお手入れのポイントもあわせてご紹介。
大切な和室を清潔に保つために、ぜひ参考にしてください。
| この記事で分かること |
| ・障子にカビが生える原因 ・障子に生えたカビの取り方 ・障子のカビを防ぐ方法 ・和紙製とプラスチック製の障子の比較 |
目次
障子にカビが生える原因とは?!
カビは温度、湿度、栄養分の三つの要素がそろうことで発生します。
障子紙と障子の木枠はどちらも水分を吸収しやすい性質をもっています。
冬の期間は外気温と室内の温度差で特に窓の結露が発生しやすく、結露の湿気を障子や木枠が吸収してカビが生えやすくなります。
また、障子がある部屋であたたかい鍋や焼き肉のような湿度が上がってしまう調理をすると障子にカビが生えてしまう原因となることがあります。
障子がある部屋で鍋や焼き肉をした場合には、換気扇を回したり、すぐに換気をするようにして部屋に湿気がこもらないようにしましょう。
また、カビは発生するとそこから胞子を飛散させて次々と新たな場所に増えていきます。
例えば、障子にカビが生えることで木枠にもカビが生え
- 和室の壁
- ふすま
- 天井
- 畳
- 押し入れ
など、どんどん増えていき、やがて部屋全体がカビに汚染されてしまうことにもつながります。
■関連記事■新築の畳はカビやすいって本当!?畳の青カビを簡単に除去する方法と再発予防策を解説
■関連記事■【襖のカビ取り】和室の襖にカビが生える原因とプロ直伝の除去方法・予防策を徹底解説!
■関連記事■押入れ・クローゼットのカビ&湿気対策ガイド|開けっ放しは効果的?白カビ・茶色いシミの掃除法
エアコンがカビを飛散させているかも?!

室内の乾燥に役立つエアコンですが、送風ファンなどエアコンの内部にホコリや汚れが付着していたり、エアコンをつけるとカビ臭がしていませんか?
エアコンの送風ファンについたホコリのように見えるものはカビであることがあります。
そのような状態でエアコンを使用すると室内にカビを飛散させてしまいます。エアコンは冷房によって内部が結露し、暖房にすると乾燥します。
障子の近くにエアコンがある場合には、エアコン周りが冷えて結露し、障子にカビが発生するということもあります。
結露は冬だけでなく、夏でも発生することがあり、結露が発生するとカビの発生にもつながります。
そのためエアコンの周りやエアコン内部のフィルターやファンの掃除も心がけましょう。
エアコンを洗浄する洗剤やエアコンのクリーニング業者もあります。
さらに、エアコンの内部を掃除する機能がついたエアコンもあります。
エアコンを有効に活用することで室内を乾燥させ、カビを抑制していきましょう。
■関連記事■【保存版】久しぶりに使ったらカビ臭い!?エアコンの結露・簡単掃除・予防法まとめ

障子にカビが生えてしまったら?!
障子にカビが生えてしまった場合、障子はデリケートな素材のため、漂白剤や消毒用エタノールを使用すると障子紙が破れてしまったり、木枠を変色させてしまうこともあり、そうなってしまうと最終的には張り替えをすることになります。
また、一度カビが発生すると、しっかりカビを除去しないと時間が経って再発をくり返すこともあります。
カビは私たちが目で確認できる状態になっているときにはかなり汚染が進行している状態です。
そのため、カビが発生してからの治療よりカビが発生しないようにしっかりと予防していくことが大切です。
障子紙のカビ取り
カビの程度が比較的軽度の場合には、漂白剤を使用した対処が可能です。
使用するものは
- 綿棒
- 漂白剤またはカビ取り剤
- コップなどの容器
- ぞうきん
です。
(↑お掃除用綿棒)
【手順】
①まずコップなどの容器に漂白剤等を少量入れます。
②綿棒の先に漂白剤等を少量含ませてやさしく障子のカビが生えている箇所に軽くあてるようにします。
③乾くのを待って完了です。
強い力で擦るようにしたり、綿棒に含ませる量が多い、劣化している障子紙などは破れてしまうおそれがありますので注意してください。
また、日焼けして黄ばんでしまっている障子紙や木枠の部分に漂白剤等がついてしまうと変色の原因となることがありますので気を付けてください。
自分でするのが不安な方や自信がないという方は専門の業者に依頼するのが確実です。

木枠のカビ取り
①カビが生えている木部を水で濡らして湿らせます。
②その後漂白剤を塗り、5分程度放置します。
(使用する漂白剤は弱アルカリ性の酸素系漂白剤がおすすめです)
これに対し、塩素系漂白剤はアルカリ性です。
アルカリ性が高くなればなるほど、洗浄力は強くなりますが、素材へのダメージも強くなります。
そのため、木枠は塩素系漂白剤を使用すると傷んでしまうことがあります。
酸素系の漂白剤は塩素系の漂白剤に比べて洗浄力は弱いのですが、木枠へのダメージも少なく済みます。
漂白剤は原液で使用すると作用が強い場合があるので、水で10倍に希釈し、カビの状況によって少しづつ濃度を上げて様子を見るのが良いでしょう。
木枠の木目にカビが入り込んでいることがあるので、歯ブラシなどを使用して塗るのがおすすめです。
その後、濡れぞうきんで漂白剤を拭き取り、扇風機やドライヤーでしっかり乾かして完了です。
併せて消毒用エタノールを吹き付けておくと殺菌効果があるのでさらにカビ予防になります。
木枠にカビが発生したまま放置しておくと最悪の場合腐ってしまうこともありますので気をつけたいですね。

グラフィコ オキシクリーン
出典:Amazon

ドーバー パストリーゼ77
出典:Amazon

しっかりとカビ取りするなら、カビ取り業者のハーツクリーンが開発したカビ取りマイスターをおススメします。
危険な成分は含まれていない為、木枠のカビ取りにも使用できます。
また、実際に業者が使用している液剤を誰でも使えるように改良した商品なので、自宅でプロレベルのカビ取りができます。

カビ取りをする際の注意点

漂白剤等を使用するため、必ず部屋の換気をしましょう。
変色や脱色の原因となってしまいますので、畳や床などに漂白剤が垂れないようにしましょう。
マスクやゴム手袋などを着用して安全な状態でおこなってください。
漂白剤を塗るときは最初に目立たないところで色落ちなどがないか確認してから全面に行うと安心です。
頑固なカビの場合には、一度で落ちないことがありますので何度かくり返し実施してみましょう。
障子のホコリや汚れがたまりやすいのはココ!
障子は桟の部分と敷居の部分に特にホコリが溜まりやすいです。
サッシ用のブラシ、歯ブラシなどを使用すると桟や敷居などの細かい部分のホコリを落としやすいです。
障子は乾いたハンディモップやはたきなどでホコリを落としましょう。
モップ部分が汚れたら洗ってくり返し使用できるハンディモップなども販売されており経済的です。
ホコリをはらうときには上から下に向かって掃除をしていくのがポイントです。
最後に下に落ちたホコリを掃除機でまとめて吸い取りましょう。
ホコリの原因となるのは主に衣類などの布製品の繊維のクズです。
部屋に布製品を極力減らすようにするとホコリの発生を防ぐことができます。
障子のカビ防止対策は?!
障子のカビを防ぐためには部屋の「換気」が重要です。
天気が良い日に窓を開けて室内の汚れた空気を外に出し、清潔な空気を入れましょう。
雨の日や、晴れていても前日が雨だった日は外の湿度が高いので窓を閉め、エアコンのドライ運転や除湿モード、除湿器等を使用しましょう。
また、空気清浄機を使用すると空気中のカビ除去効果も期待できるので有効に活用していきたいですね。
結露対策と消毒でカビを防ぎましょう
結露が発生している場合にはこまめに拭き取るようにして障子紙や木枠が湿気を吸収してしまわないようにしましょう。
結露防止シートなどの結露対策アイテムを使用すると、結露の拭き取りの負担が軽減されるのでおすすめです。
さらに月に一度程度、障子に消毒用エタノールを吹き付けておくとカビが発生するのを防ぐことができます。
消毒用エタノールは揮発性が高いため、吹き付けたあとは拭き取る必要がありません。
障子以外のカビ対策でも消毒用エタノールは活躍してくれますので、ドラッグストアなどで購入して用意しておくことをおすすめします。
■関連記事■結露によるカビ発生を防ぐ方法とは?湿気対策の基本と予防策7選
プラスチック製の障子紙も
障子紙には和紙の他に、プラスチック製の障子紙というものがあります。
プラスチック製の障子紙は薄い塩化ビニール製のシートで和紙を挟んで作られています。
様々なメーカーから障子用ののりを使用して貼るタイプやアイロン、両面テープを使用して貼るものまで種類が豊富で、ホームセンターなどでも購入することができます。
和紙は破れたり、汚れやすいので、お子さんやペットがいるおうちでは交換する頻度が高くなってしまうこともあるかもしれません。
そこで、日焼けや破れや汚れに強い丈夫な障子紙としてプラスチック製の障子紙があります。
強度をアップすると通気性は悪くなってしまうため、明るさなどが素材によって異なります。
プラスチック製の障子は丈夫ですが、結露が発生した場合には拭き取るなど手入れをしないでいると木枠の部分などにカビが生えてしまうことがあります。
それぞれの障子紙のメリット・デメリット
| 和紙 | プラスチック製 | |
| 価格 | 低 | 高 |
| 通気性 | ○ | × |
| 耐久性 | 弱 | 強 |
| 貼り替え頻度 | 多 | 少 |
| 水拭き | 不可 | 可能 |
【カビ最新ニュース】豪雨増加で和室のカビ被害が拡大
近年はゲリラ豪雨や長時間の強雨が増え、住宅の室内湿度が上昇しやすくなっています。
2025年8月6日〜12日の記録的豪雨では、九州・四国・近畿を中心に線状降水帯が相次ぎ、気象庁の速報では広い範囲で3時間・24時間降水量が観測史上1位を更新しました。
総降水量600mm超や、平年8月の3倍以上となった地点も報告されています。
総務省消防庁によると全国で5,000棟以上が浸水し、浸水被害がなかった住宅でも「障子・ふすま・畳にカビが出た」という相談が急増しました。
豪雨後は結露や床下の湿気が残りやすく、障子紙のシミ、青カビの発生、木枠の黒ずみ、和紙の湿り気などが多く見られます。
和紙や木材は湿気を吸いやすいため、表面を拭いても内部に水分が残っているとカビが再発しやすくなるので注意するようにしましょう。
大雨のあとに障子の変色・木枠のカビ・部屋のカビ臭が出てきた場合は、早めに乾燥と換気を行い、必要であれば専門業者に相談することが推奨されています。
参考:気象庁|低気圧と前線による大雨
障子のカビに関するQ&A
Q1. 障子紙の薄いカビは自分で取れる?
軽度の点状カビなら、綿棒+薄めた漂白剤で軽く当てると薄くなることがあります。
ただし紙が劣化していたり広い範囲に出ている場合は、破れやすいため張り替えた方が良いでしょう。
Q2. 木枠のカビに塩素系漂白剤を使ってもよい?
木材は傷み・変色しやすいため避けた方が無難です。
まず水で湿らせ、薄めた酸素系漂白剤を歯ブラシで塗布→拭き取り→十分な乾燥、の流れが安全です。
仕上げに消毒用エタノールを吹きかけると再発防止にもなります。
Q3. 一度落としてもすぐに戻るのはなぜ?
結露や換気不足など、湿気の原因がそのまま残っているケースが大半です。
窓まわりの結露拭き・晴れた日の換気・除湿運転・障子周辺の通気改善など、環境対策をセットで行うことで再発を大幅に抑えられます。
まとめ|障子のカビは「早めの対処」と「予防ケア」がポイント
障子にカビが発生してしまっても、早めに適切な方法で対処すれば自分で落とすことは可能です。
特に和紙部分はデリケートなため、中性洗剤や消毒用エタノールなどを素材に合わせて使い分けることが大切です。
また、再発を防ぐには、こまめな換気や結露対策、カビに強い障子紙の選定など、日常的なケアが欠かせません。
障子は和室の雰囲気を大きく左右する存在です。
清潔な状態を保つことで、空間全体の印象も大きく変わります。
カビに負けない障子づくりのために、今回の記事を参考にぜひ実践してみてください。
<参考文献>
・山田芳照『NHK住まい自分流DIY入門DIYの素材と道具図鑑』2007年、NHK出版
・蓮見清一『パパッとさんのおそうじと収納のコツと基本』2012年、宝島社
・朝倉邦造『カビのはなし‐ミクロな隣人のサイエンス‐』2013年、朝倉書店
・浜田信夫『人類とカビの歴史 闘いと共生と』2013年、朝日新聞出版








コメント