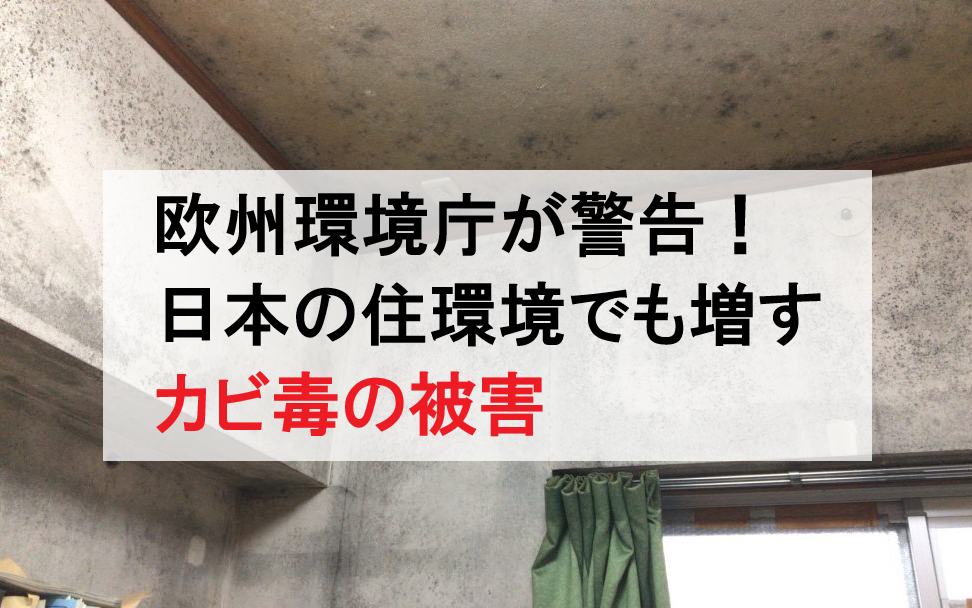
地球の気温が少しずつ上がっている今、思わぬ健康リスクが、私たちのすぐそばにまで迫ってきています。
欧州環境庁(EEA)は最新の報告で、「カビ毒(マイコトキシン)」と呼ばれる有害物質への注意を呼びかけました。
参考:欧州環境庁、気候変動が食品のカビ毒汚染への曝露リスクを高めていると報告
カビ毒は食品や飼料などに生えたカビが作り出す毒で、体にさまざまな悪影響を及ぼすことがわかってきています。
例えば、免疫力の低下やホルモンバランスの乱れ、さらに長期間の摂取による発がんリスクなどが指摘されています。
しかもこれは欧州だけの話ではありません。
湿気の多い日本でも、気温の上昇とともに、今後こうしたリスクがさらに高まる可能性があります。
この記事では、カビ毒の危険性や、今日から実践できる対策について解説します。
知らないうちに体に入ってくる「見えないリスク」から、大切な家族と暮らしを守るために、ぜひ最後までお読みください。
| この記事でわかること |
| ・カビ毒(マイコトキシン)とは何か ・なぜ日本でもリスクが高まっているのか ・カビ毒が健康や暮らしに与える影響 ・今すぐできるカビ対策方法 |
目次
1. カビ毒(マイコトキシン)とは?

「カビ毒」や「マイコトキシン」という言葉を聞いても、馴染みのない方も多いでしょう。
そこでまずは、カビ毒とは何か、そしてどのような危険性があるのかを詳しく解説します。
1-1. カビが作り出す有害物質
カビ毒(マイコトキシン)とは、カビが繁殖する過程で作り出す有害な化学物質の総称です。
私たちの身近なところでは、穀物、パン、パスタ、ナッツ類、乾燥果物などの食品にカビが生えた際に、そのカビからカビ毒が産生されることがあります。
この物質はごく微量でも、長期的に体内に取り込まれることで健康への悪影響を引き起こす可能性があるため、世界的に問題視されています。
とくにアフラトキシンやデオキシニバレノールといった種類は、発がん性や免疫抑制作用があることがわかっており、厳しく監視されています。
参考:農林水産省|いろいろなかび毒
参考:厚生労働省|かび毒評価書デオキシニバレノール及びニバレノール(第2版)
1-2. 欧州環境庁(EEA)の警告
欧州環境庁(EEA)が発表した報告によると、欧州ヒト・バイオモニタリング・プロジェクト(HBM4EU)の調査で、ヨーロッパの成人のおよそ14%が、健康に悪影響を与えるおそれのある量のカビ毒「デオキシニバレノール」を日常的に体に取り込んでいる可能性があることが明らかになりました。
気温や湿度の上昇によってカビの繁殖が促されると、穀物や飼料、食品の安全性に対するリスクがさらに高まります。
つまり、気候変動が進めば進むほど、カビ毒の問題もより深刻になると考えられているのです。
住まいの「カビが増えやすさ」も先に確認しておく
欧州環境庁の報告が示すように、カビ毒への曝露リスクは気候だけでなく、身の回りの環境条件によっても左右されます。
日本でも、住まいの湿気のたまり方や換気のしやすさによって、室内でカビが発生しやすい状態かどうかは大きく変わります。
気になる方は、以下の診断を活用してご自宅がどの程度カビが発生しやすい状態かをチェックしてみてください。
2. 日本でも「カビ毒リスク」は他人事ではない
これまでお伝えしてきたカビ毒の問題は、ヨーロッパに限った話ではありません。
日本でも、気候や住環境の特徴から、カビ毒のリスクは身近な問題になり得ます。
2-1. 高温多湿な気候はカビが好む環境

日本は四季がある国ですが、梅雨や夏場の長雨、蒸し暑い日が続く時期は、カビにとって非常に繁殖しやすい条件がそろっています。
近年では、ゲリラ豪雨や猛暑日といった極端な気象の増加も報告されており、農作物や食品にカビが発生するリスクが高まっています。
実際、気象庁の観測データによると、日本の年平均気温は100年あたり約1.26℃のペースで上昇しており、これに伴って1時間に50mm以上の大雨(集中豪雨)が発生する回数も長期的に増加傾向を示しています。
こうした温暖化と降水量の増加により、夏場の高温多湿の状況が強まることが指摘されています。
また、湿度が高くなりがちな日本の住まいでは、室内でもカビが発生しやすくなる点にも注意が必要です。
カビ毒を含む胞子が空気中に広がると、それを吸い込んでしまい、知らないうちに体内へ取り込むリスクが高まります。
在宅時間が長くなると、その分だけカビに触れる機会も増えるため、日常的な対策が重要になってきます。
参考:気象庁|日本の年平均気温
2-2. カビ毒が引き起こす主な健康被害
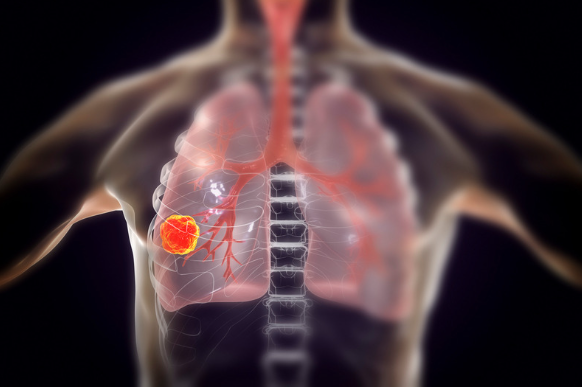
マイコトキシン(カビ毒)を長期間にわたって体に取り込み続けると、以下のような健康リスクがあるとされています。
- 免疫力の低下
- ホルモンバランスの乱れ
- 呼吸器系の病気の悪化(喘息や気管支炎など)
- アレルギー症状(鼻炎や皮膚炎など)
- 長期的には発がんのリスクも
食品や飼料はもちろん、住まいの中に発生したカビが放出するマイコトキシンにも注意が必要です。
とくに子どもや高齢者、持病のある方は影響を受けやすいため、日常の中で「カビを増やさない・取り込まない」工夫がとても大切です。
■関連記事■カビの発がん性リスクを徹底解説!カビから身を守る9つの対策法とは?
2-3. 気候変動によるカビ発生リスクと経済的損失
欧州環境庁(EEA)の報告では、穀物がカビに感染することで収穫量が減少し、経済的な損失が発生する恐れがあることが指摘されています。
さらに、カビの発生を抑えるために殺菌剤の使用量が増加する可能性もあり、環境への負荷も懸念されています。
こうした問題は日本でも起こり得ます。
台風、集中豪雨、猛暑などの極端な気象の影響で農作物が弱り、カビが発生しやすくなるケースが今後さらに増えると考えられます。
農作物がカビに弱くなれば、それを通じて私たちの食卓にのぼる食品にもカビ毒が含まれるリスクが高まることになります。
つまり、気候変動は、農業や経済だけでなく、私たちの健康や日々の食生活にも深く関係する問題といえるでしょう。
3. 室内のカビ対策がますます重要に
日本の住まいは、気候変動やライフスタイルの変化によって、これまで以上にカビが発生しやすい環境になってきています。
たとえば、高気密・高断熱の住宅が増えていることや、在宅時間の増加などがその一因です。
室内に発生したカビをそのまま放置しておくと、カビ毒が空気中に広がり、健康リスクにつながるおそれもあります。
家族の健康を守るためにも、以下のような対策を日常的に取り入れることが大切です。
3-1. こまめな換気と湿度管理
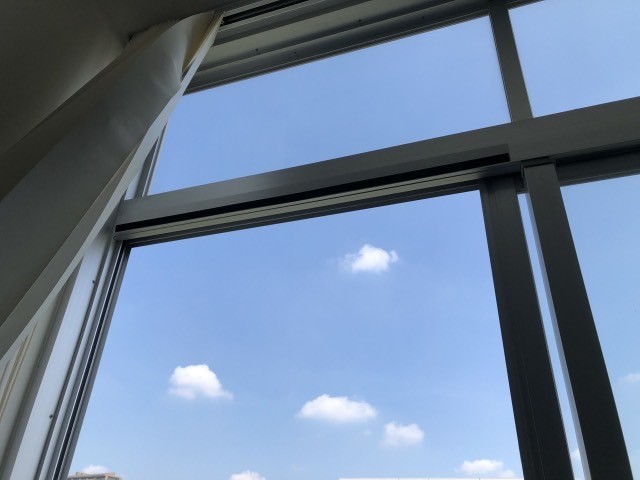
カビの繁殖を防ぐためには、室内の湿度を適切に保ち、こまめに換気を行うことが大切です。
理想的な湿度は50〜60%とされており、特に梅雨や夏場は湿気がこもりやすいため注意が必要です。
エアコンや除湿機、換気扇などを上手に活用し、室内に空気の流れをつくることで、カビの発生を抑えることが可能です。
3-2. 定期的な清掃と点検
カビは、エアコンや換気扇、押し入れ、クローゼットなどの湿気がこもりやすい場所に発生しやすいため、定期的な掃除が大切です。
見えにくい場所ほどカビが見逃されがちですが、小さなうちに発見・除去することで被害の拡大を防ぐことができます。
こまめな点検と清掃を習慣にすることが、室内のカビ対策の基本です。
3-3. 専門業者によるカビ対策
一度広範囲にカビが発生してしまうと、目に見える部分だけでなく、壁や天井の内部まで根を張っているケースが多くなります。
そうした場合には、家庭での掃除では取り切れないため、専門業者に除去してもらうのが安心です。
プロによる専用の液剤や機材を使った施工で、再発防止まで含めた安全なカビ対策が可能になります。
■関連記事■【2026年版】カビ取り業者の選び方|失敗しない依頼ポイント&おすすめ業者比較
■関連記事■【2026年版】カビ取り業者の費用相場|間取り・場所別の料金比較&選び方

4. まとめ
欧州環境庁の報告が示すように、気候変動によってカビ毒(マイコトキシン)のリスクが世界的に高まっており、その影響はヨーロッパだけでなく、高温多湿な気候を持つ日本にも及んでいます。
食品や飼料への影響はもちろん、住宅内でもカビが繁殖しやすくなり、健康被害や経済的損失を引き起こす可能性があります。
目に見えないカビ毒は、知らないうちに生活に入り込み、アレルギーや呼吸器疾患などの体調不良の原因になることもあります。
カビの発生やニオイ、アレルギー症状が気になる場合は、できるだけ早い段階で専門業者に相談することをおススメします。
家族が安心して過ごせる環境づくりのためにも、小さな変化を見逃さず、早めの対策を心がけましょう。








コメント