意外な盲点!身近な金属がカビる原因と自宅で簡単にできるカビ取り&予防方法
ふと気が付くと、金属製のアイテムが黒ずんだり白っぽく汚れていた・・・。
「金属にカビなんて生えるの?」と疑問に持つ方も多いのではないでしょうか?
実は金属も、条件が揃えばカビが発生することがあるのです。
放っておくと見た目が悪くなるだけではなく、劣化やサビの原因になってしまうことも。
また、金属特有の汚れ「緑青(ろくしょう)」をカビと間違えることも多いので、正しく見極めることが大切です。
この記事では、金属にカビが生える原因や緑青との見分け方、簡単にできるカビ取り方法、さらにカビを防ぐためのお手入れのコツまで詳しくご紹介します。
金属製品を清潔に保つため、ぜひ最後までお読みください。
| この記事で分かること |
| ・金属にカビが生える原因 ・自宅で出来る金属のカビ取り方法 ・金属のカビを予防する方法 |
目次
1. 身近な金属
身近な金属というと銅、鉄、アルミニウム、ステンレス、銀、金などがあります。
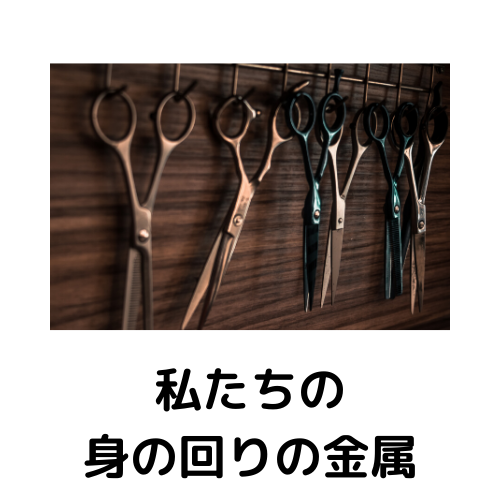
金属が使用されている身近な製品は、シンク、蛇口、窓枠、缶、水筒、スプーンやフォーク、包丁やナイフ、ハサミなどの刃物、鍋、やかん、フライパン、針、釘、鍵、郵便ポスト、硬貨、アクセサリー、カバンやバッグなどの金具、機械や日用品などたくさんの物に使用されています。
■関連記事■ピアスやイヤリングにカビが!?原因と自宅で簡単にできる6つの除去方法を解説
2. 金属にカビが生える原因とは?
金属は無機物質のためカビが発生しない素材です。
これはカビが金属そのものに留まって繁殖したり、金属を食べたり栄養分とすることはないということです。
しかし、金属は木材やプラスチックなどに比べて丈夫で頑丈なイメージがありますが、使用していくうちに金属の表面には細かな傷や溝ができてしまっていることがあります。
すると、その傷や溝にホコリや手あか、食品などの汚れがたまっていきます。
そこにカビの好む湿度や温度の条件がそろうことでホコリや汚れが栄養源となり、カビが発生するのです。
そのため、金属についたホコリや汚れを放置することがカビの繁殖の原因となります。
2-1. まずは本当にカビかどうかの確認もしましょう。
金属にカビが生えてしまった!というときは、まずカビかどうかの確認もしてみてください。
金属にカビが生えてしまったと思ったら実はサビだった!ということもあります。
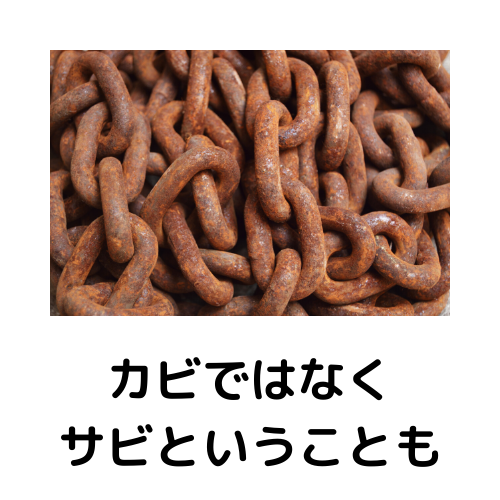
洗剤で洗浄して汚れを除去したあとに残ってしまう黒や赤の汚れはカビであると考えられます。
2-2. カビと見間違えやすい「緑青」とは?!
よく青カビと間違われるのが金属にできるサビである「緑青(ろくしょう)」です。
緑青は銅が酸化して起こる現象で、鎌倉の大仏や自由の女神など緑色になっていますよね?

これは銅に付いた緑青によるものです。
金属のサビは市販のサビ取り剤を使用すると除去することができます。
また、金属に白いザラザラしたものや点々ができることがあります。
一見白カビのように見えますが、これは水に含まれるカルキなどの成分でそのような状態になっています。
この場合には擦り取ろうとすると金属に傷がついてしまうので専用の洗剤を使用することで除去することができます。
3. 金属のカビ取り方法
3-1. 金属に使用できるカビ取り剤を使用する方法
用意するものは、金属に使用できるカビ取り剤、ゴム手袋、マスク、メガネやゴーグル

金属はカビキラーやキッチンハイターなど塩素系の薬剤を使用してカビを除去しようとすると腐食してサビの原因となってしまうため使用することができません。
しかし、薬剤の種類によっては金属にも使用できる商品もあります。
例えば、キッチン泡ハイターはスプレーして2~5分で洗い流すタイプなのでステンレス製品に限り使用することができます。
スプレーしたあとはしっかり洗い流すようにすることでサビを防ぐことができます。
ステンレス製品以外の金属には使用することができませんので注意してください。
※注意点※
カビ取り剤を使用するので必ず換気をしながら作業をしてください。

また、衣服にカビ取り剤が付着すると漂白されて色が抜けてしまうので注意してください。
酸性の洗剤等と混ざると有毒なガスが発生して危険ですので注意してください。

花王 キッチン泡ハイター
出典:Amazon
3-2. 消毒用エタノールを使用する方法
用意するものは消毒用エタノール、スプレーボトル
消毒用エタノールを金属にスプレーしてカビを殺菌・消毒しましょう。
※注意点※
消毒用エタノールは引火しやすいのでキッチンまわりや火気があるところで使用する際には注意してください。
消毒用エタノールが揮発するまではタバコやライターなども使用しないでください。

ドーバー パストリーゼ77
出典:Amazon
3-3. 熱湯を使用する方法
用意するものは熱湯、鍋、熱めのシャワーなど
50℃以上の熱いシャワーをかける。
熱湯を継続的にかけることでカビを死滅させることができます。
カビは肉眼で確認できる状態になっているときはかなり繁殖している状態なので内部まで奥深く根をはっています。
そのため、熱湯を表面にサッとかけただけでは簡単にはカビは死滅しないのです。
内部までしっかりと熱を伝えるためには1~2分熱いシャワーをかけ続ければ十分でしょう。
熱湯消毒も煮沸消毒もカビを死滅させることができますが、カビによる黒ずみを落とすことはできません。
※注意点※
製品によっては煮沸消毒すると変形してしまったり、傷んでしまうものもありますので取り扱い説明書等で確認してからおこなうようにしてください。
金属は熱伝導が良いため、熱湯で高温になりますのでやけどに注意してください。
3-4. 物理的に削り取る方法
用意するものは下記のいずれかのものです。
- 重曹
- クリームクレンザー
- メラミンスポンジ
- スチールウール
- 抗菌スポンジなど
これらのものは金属に生えたカビを削り取る役目をします。
銅の力でカビ予防ができる抗菌スポンジや抗菌タワシという商品が販売されています。
銅には優れた抗菌性があり雑菌が繁殖するのを防ぎ、銅の細かな粒子がクレンザーの役目となり汚れを落とすことができます。
粒子が球状なので使用しても傷がつきにくいため、銅の抗菌スポンジやタワシはおすすめです。
カビが取れたらしっかりと金属の水分を拭き取り、乾燥させましょう。
乾いたら消毒用エタノールを噴霧しておくことでカビの予防もできます。
※注意点※
金属に傷がついてまたそこに汚れがたまる原因にもなりますので注意が必要です。

シャボン玉石けん 重曹
出典:Amazon

レック 激落ちくん キューブ
出典:Amazon
3-5. 中性洗剤を使用する方法
- 用意するものは
- 中性洗剤
- スポンジ(タワシ)細かい部分には歯ブラシ
などがあると便利です。
比較的軽度のカビであれば中性洗剤で落とすことができます。
中性洗剤をスポンジや歯ブラシにつけてカビが生えている箇所をこすって落とします。
カビが落とせたら金属の水分をしっかり拭き取って乾燥させ、仕上げに消毒用エタノールを噴霧しておくとカビの予防ができます。
4. 金属のカビを予防する方法
4-1. こまめな掃除を
金属のカビを予防するために、金属製品を使用したあとは掃除をして清潔にすることが重要です。
カビは一度発生するとどんどん繁殖して増えていきます。
一度増殖したカビは完全に根絶させるのが難しく、手間もかかります。
金属を掃除する際には、腐食など劣化の原因となってしまいますので、アルカリ性や酸性の洗剤の使用は避けた方が良いでしょう。
4-2. 傷に注意
また、クレンザーのような研磨剤が入っている洗剤を使用すると金属の表面を傷つけてしまうことになり、そこに汚れがたまってしまうため、普段の手入れでは、できれば使用しない方が良いです。
カビが肉眼で確認できなくても、定期的に消毒することを心がけることでカビを発生させないようにすることができます。
4-3. カビは早めに対処する
また、カビが発生してしまった場合にも早期発見し、すぐに対処することでカビを初期段階で死滅させ、定着させないようにすることが大切です。
熱湯消毒や煮沸消毒のあとは部屋の換気と水分を拭き取り、金属をしっかり乾燥させることも重要です。
金属にカビを発生させないために、普段からこまめに換気して部屋の中の風通しを良くすることも大切です。
換気扇を回したり、窓を開けて換気をしましょう。
4-4. 除湿機やドライ機能を活用

雨の日などは窓を開けてしまうと湿気が入ってきてしまうので、窓を閉めて扇風機やサーキュレーターで室内の空気を循環させ、部屋の湿度が高い場合には、エアコンのドライモードや除湿機を活用しましょう。
金属製品を戸棚などにしまっている場合には、ときどき戸棚の扉を開放して中の空気を循環させましょう。

5. まとめ
金属そのものはカビの栄養源になりませんが、表面のホコリや皮脂汚れにカビが付着・繁殖することがあります。特に水まわりや湿度の高い場所では要注意です。
また、緑青(ろくしょう)やサビ、カルキ汚れなどをカビと誤認しやすいため、見た目だけで判断せず、正しく見極めて対処することが重要です。
カビを落とすには、素材に合った洗剤や方法を選ぶことがポイント。ステンレスにはキッチン泡ハイターが使える場合もありますが、他の金属には腐食の原因になるため注意が必要です。消毒用エタノールや熱湯、重曹・抗菌スポンジなど、対象物に適した方法で除去・予防しましょう。
カビの発生を防ぐには、以下のような日常的な習慣が効果的です。
- 金属表面をこまめに掃除し、汚れを残さない
- 傷をつけず、通気・乾燥を意識した保管
- 湿度管理を行い、換気や除湿を徹底
金属製品は長く使えるものだからこそ、正しいケアで清潔に保ち、カビによる劣化や見た目の悪化を防いでいきましょう。

