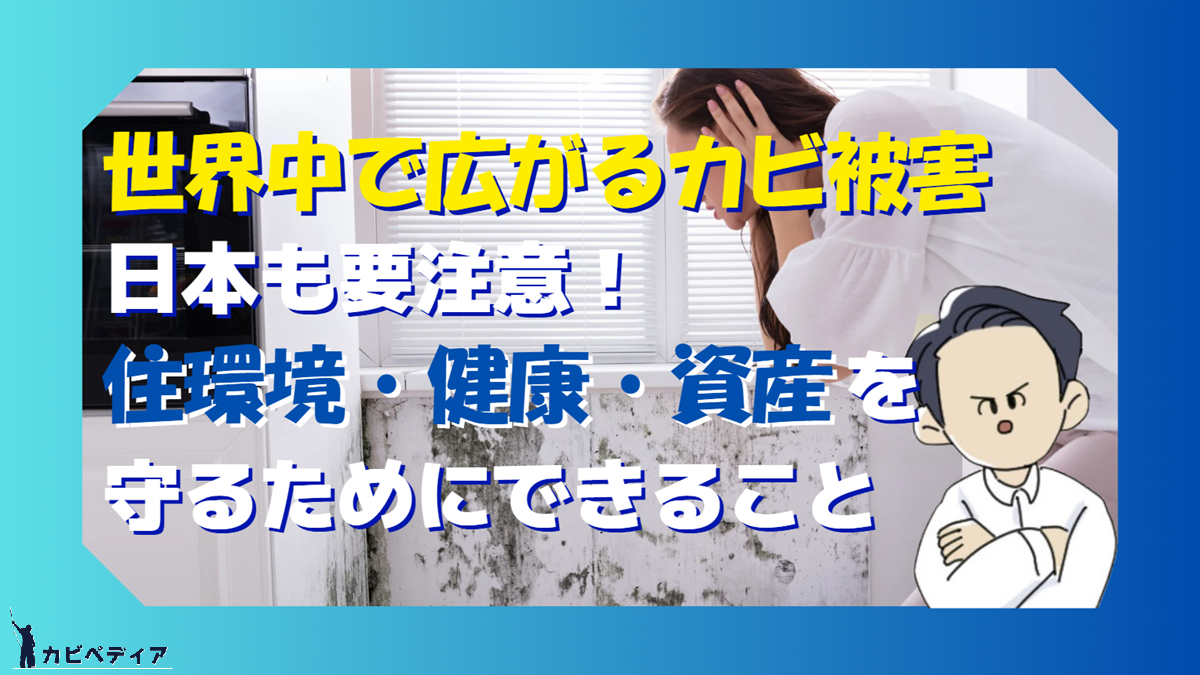
近年、世界各地でカビによる被害が深刻化しているという報道が相次いでいます。
そして新たにデンマークの美術館・博物館で深刻なカビ被害が発生しました。
ガーディアン紙によると、これらの施設では新種の白カビが確認され、貴重な文化財を劣化させているといいます。
デンマークの美術館・博物館で新種のカビが所蔵品を損傷。専門家は「国内だけの問題ではない」と警鐘
しかし、この問題は決して遠い国の出来事ではありません。
カビは美術品だけでなく、私たちの住まいや健康にも深刻な影響を及ぼす存在です。
特に高温多湿な日本では、住宅内でのカビ発生リスクが高く、放置すれば建物の劣化や健康被害、資産価値の低下につながる恐れがあります。
本記事では、デンマークでの最新事例をもとに、カビの驚くべき繁殖力や私たちの暮らしに及ぼすリスクを解説します。
あわせて、今すぐ取り入れたいカビ予防の基本や、専門業者に相談すべきタイミングとその重要性についても詳しく紹介します。
目次
1.デンマークの博物館・美術館で発見された新種の白カビ

デンマークの美術館で、新種の白カビが文化財を侵食していることが明らかになりました。
ガーディアン紙によると、従来のカビ対策では対応が難しく、専門家も深刻な問題として警鐘を鳴らしています。
1-1.新種の白カビが文化財を脅かす
デンマーク国内の複数の美術館・博物館で、アスペルギルス属レストリクティ節に分類される新種の白カビが確認されました。
このカビは、「epidemic for Golden Age paintings(黄金時代の絵画に対する疫病)」と呼ばれ、絵画や文化財に付着すると酵素で表面を分解しながら劣化を進行させるという、極めて厄介な性質を持っています。
美術品の保存・保全に深刻な脅威となっており、専門家の間で警戒が強まっています。
1-2.低湿度環境でも繁殖するカビ
一般的にカビは高湿度の環境で発生しやすいとされていますが、今回の白カビは例外です。
低湿度でも繁殖可能であることが確認されており、極限環境とされる深海や火山地帯でも生存できるほどの耐性を持っています。
このような性質から、従来の「湿度管理」や「換気」といった基本的なカビ対策だけでは防ぎきれず、より高度な環境管理が求められる状況となっています。
1-3.デンマークだけの問題ではない
デンマーク国立博物館の保存・コレクション保管部長は、「これはデンマークだけの問題ではなく、世界中で起きている可能性がある」と語り、国際的な危機意識の必要性を訴えています。
実際、カビは国境や気候を問わず存在する微生物であり、美術館や博物館に限らず、私たちの日常生活や住環境にも深く関係する問題です。
日本にも同じカビがすでに存在している可能性は否定できません。
もしそうなら、日本の美術館や博物館も同様のリスクにさらされていることになります。
湿度の高い日本では、従来の対策だけでは不十分な場合もあるため、今こそ防カビ環境の見直しが求められます。
日本の住まいでも「カビが起きやすい条件」は変わる
デンマークの事例が示すように、カビは想像以上にしぶとく、環境条件しだいで被害が一気に広がることがあります。
日本でも、住宅の湿気のたまり方や換気のしやすさなどによって、同じ季節でもカビの起きやすさは大きく変わります。
気になる方は、以下の診断でご自宅がどの程度カビが発生しやすい状態かをチェックしてみてください。
2.カビがもたらす様々な被害

カビの被害は美術品だけにとどまりません。
住宅や建物の構造、さらには人の健康にも影響を及ぼす可能性があります。
2-1.文化財や美術品へのダメージ
デンマークの事例が示すように、カビは絵画・木工芸品・紙資料などの文化財を劣化させる原因となります。
カビが分泌する酵素が素材を分解し、保存を困難にするだけでなく、外観の損傷が進行すれば修復も困難になります。
そのため、文化遺産保護の観点から見ても、カビは極めて深刻な脅威です。
■関連記事■文化財・絵画がカビの危険に!プロが教える予防策と個人でできる対処法
2-2.建物や住環境への影響

カビは建築物にも侵入し、壁紙・木材・断熱材などに被害を与えることがあります。
特に湿度が高い日本の住宅では、浴室・キッチン・押し入れなどの閉鎖空間でカビが繁殖しやすく、悪臭や見た目の劣化だけでなく、住環境の快適性を損なう要因となります。
放置すればカビが広がり、高額な修繕費がかかることもあるため、早めの対処が大切です。
2-3.健康リスクとアレルギー症状
カビの中には、人体に悪影響を及ぼす種類も存在します。
アスペルギルス属のカビは、免疫力が低下している人に対して慢性肺アスペルギルス症などの疾患を引き起こす可能性があります。
また、カビの胞子を吸い込むことで、喘息やアレルギー反応を引き起こすリスクも高まります。
小さなお子さん、高齢者、体調を崩している方などは特に注意が必要です。
3.日本でも求められるカビ対策の重要性

カビの問題は、決して海外だけの話ではありません。
日本は高温多湿な気候により、カビが発生・繁殖しやすい環境が年間を通して続きます。
ここでは、日本特有のリスクと対策の必要性について見ていきます。
3-1.湿度が高い日本特有の環境
デンマークで確認された新種カビは低湿度でも繁殖しますが、日本ではそもそも湿度が高くなる期間が長く、多様なカビが発生しやすいのが特徴です。
特に梅雨や台風シーズン、夏場には湿度が60〜80%に達する日が続き、結露や換気不足も重なってカビの好む条件が簡単に整ってしまいます。
そのため、湿度管理や換気を日常的に意識することが、カビ予防の基本となります。
■関連記事■【2026年版】梅雨のカビ&湿気対策完全ガイド|春から梅雨明け後まで快適に過ごせるカビ対策をプロが伝授
3-2.文化財・芸術作品への影響は国内外共通

日本国内にも、国宝や重要文化財をはじめとした貴重な美術品・歴史資料が数多く存在します。
美術館や博物館では温湿度の管理が厳重に行われているものの、それでもカビの侵入・繁殖リスクを完全に防ぐことはできません。
文化遺産を守るためには、定期的な点検・清掃・湿度管理を徹底するとともに、早期発見と迅速な対応が不可欠です。
3-3.日常生活におけるカビ対策の必要性
文化財ほどデリケートではないとしても、私たちの住まいや家具、衣類、家電などにもカビは発生します。
初期段階では見逃されがちですが、放置すると広がり、住環境の劣化や健康リスク、修繕費の増大につながる恐れがあります。
「少しくらいなら大丈夫」と油断せず、早めの対応や専門業者への相談を行うことが、被害の拡大を防ぐための重要なポイントです。
4.カビ発生を予防するための基本ポイント
カビは一度発生すると完全に取り除くのが難しく、再発のリスクも高いため、日頃から予防を意識することが何より重要です。
ここでは、住まいを清潔に保ち、カビの発生を未然に防ぐための基本的な対策ポイントを紹介します。
4-1.湿度管理の徹底

カビは湿度60%を超える環境で活発に繁殖します。
そのため、室内の湿度を常に60%以下に保つことが、予防の基本です。
特に梅雨や夏場は湿度が高くなりやすいため、除湿機やエアコンのドライ機能を活用しましょう。
湿度計を設置して数値を「見える化」するのも有効です。
寝室や収納スペースなど空気がこもりやすい場所は特に注意しましょう。

タニタ 温湿度計
出典:Amazon
4-2.換気をこまめに行う
空気の流れがない場所には湿気がたまりやすく、カビの発生リスクが高まります。
浴室やキッチンでは、調理・入浴後に必ず換気扇を使用するよう習慣づけましょう。
また、押し入れやクローゼットなどの閉鎖空間も週に1〜2回程度は扉を開けて空気を入れ替えるのがおすすめです。
晴れた日には窓を開け、自然換気を取り入れることで室内の湿気を効果的に排出できます。
4-3.清掃と乾燥を徹底
浴室や洗面所などの水回りは、カビが特に発生しやすい場所です。
床や壁、排水口まわりには石けんカスや皮脂汚れがたまりやすく、これらがカビの栄養源になります。
使用後は壁や床の水滴を拭き取り、換気をしてしっかり乾燥させる習慣をつけましょう。
また、カビを発見した場合は、初期のうちにカビ取り剤で除去することが重要です。
早めの対処であれば、簡単に落とせるケースも多く、被害の拡大を防ぐことができます。

4-4.定期点検と環境の見直し
カビを防ぐには、清掃だけでなく住まい全体の点検も重要です。
エアコンにカビが繁殖すると、稼働時に胞子が室内に広がる恐れがあるため、フィルターの清掃や点検は定期的に行いましょう。
また、水漏れや雨漏りもカビの原因になります。
壁のシミや天井の変色を見つけたら、早めの修繕が必要です。

5.もしカビを発見したら早めの対処が肝心
カビは放っておいて自然に消えることはなく、時間とともに被害が拡大していきます。
見つけた時点で適切な処置を行うことが、被害を最小限に抑える最善策です。
5-1.自力対処は初期段階まで
カビを見つけたら、まず確認すべきなのはその「広がり具合」と「発生場所」です。
壁やパッキンなどに小さな黒ずみがポツポツと見える程度であれば、市販のカビ取り剤を使って拭き取り、しっかり乾燥させることで再発を防げる可能性があります。
しかし、建材の内部まで侵食していたり、同じ場所で繰り返しカビが発生している場合は要注意です。
表面だけをきれいにしても根が残っていれば、すぐに再発してしまいます。
また、無理に強い薬剤を使うと素材を傷めてしまうおそれもあります。
状況をよく見極め、不安がある場合は早めに専門家に相談する判断力が重要です。
5-2.専門業者への相談で根本解決

カビが広範囲に広がっていたり、建材の内部まで侵食している場合は、迷わず専門業者に相談しましょう。
プロであれば、カビの種類や繁殖状況を調査し、原因に応じた根本的な対策を提案してくれます。
カビ取り専門業者のカビ取りマイスターは、5,000件以上の施工実績を持つ専門業者で、安心して任せられる存在です。
状況に応じて防カビコーティングなどの再発防止処理も行うため、繰り返すカビに悩んでいる方には特におすすめです。
「カビを再発させたくない」なら、カビ取りマイスターの利用を検討してみてください。

■関連記事■【2026年版】カビ取り業者の選び方|失敗しない依頼ポイント&おすすめ業者比較
■関連記事■【2026年版】カビ取り業者の費用相場|間取り・場所別の料金比較&選び方
5-3.美術品や貴重品などはガス滅菌がおすすめ
美術品や書籍、思い出の品などのカビ対策には、ガス滅菌が最適です。
「エチレンオキサイドガス(EOガス)」は医療機器の滅菌にも使われており、高い殺菌力を持ちながら素材を傷めにくいのが特長です。
目に見えない内部のカビまでしっかり除去でき、文化財や繊細な品の保管にも適しています。
ハーツクリーンのガス滅菌サービスなら、サイズを選んで申し込みをして、まとめて段ボールに入れて送るだけで簡単に利用可能です。
法人の方や大量の滅菌をご希望の場合は、以下のリンクよりお問い合わせください。
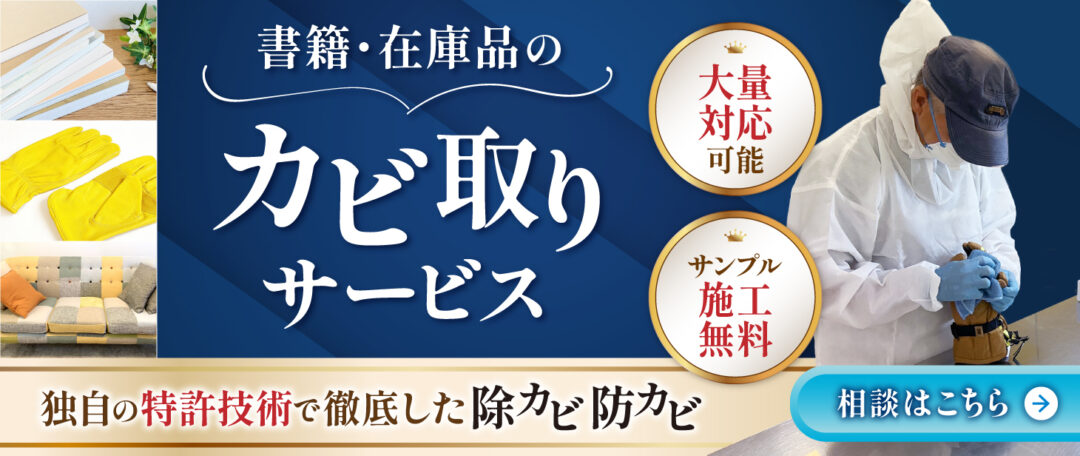
6. まとめ
今回は、デンマークの美術館で発見された新種の白カビのニュースをきっかけに、私たちの暮らしにも潜むカビのリスクについて見てきました。
高温多湿な日本では、湿度管理・換気・清掃を日常的に行い、わずかな異変にも早めに気づいて対処することが大切です。
もしカビが広範囲に広がってしまった場合は、専門業者による原因調査と根本的な対策を検討しましょう。
カビの被害は、美術品や建物だけでなく、健康や資産にも深刻な影響を与える可能性があります。
カビに悩まされない毎日のために、まずはできる対策から始めてみましょう。








コメント