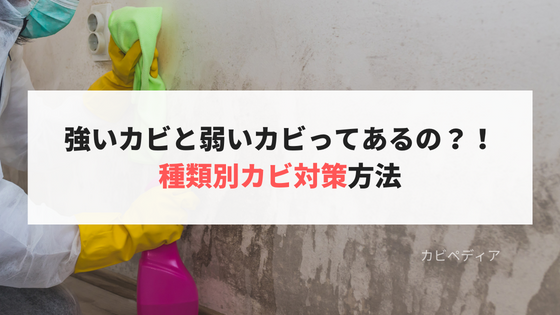

『カビ』と言ってもさまざまな種類があり、発生しやすい場所や除去の仕方に違いがあることをご存じでしょうか?
生命力が強く、除去が難しい「強いカビ」や、早めの対処で簡単に除去できる「弱いカビ」も存在します。
家の中に生えやすいカビの種類を知っておくことで、より適切な予防や対処ができるようになりますよ。
この記事では、家庭内でよく見られる代表的な4種類のカビ(黒カビ・青カビ・白カビ・赤カビ)の特徴と、それぞれの効果的な除去方法を詳しく解説します。
さらに、毎日の習慣に取り入れられるカビ予防のポイントも紹介しますので、カビにお悩みの方はぜひ参考にしてくださいね。
| この記事でわかること |
| ・家庭に発生しやすいカビの種類と特徴 ・カビの種類別の除去方法 ・カビを防ぐための対策方法 |
目次
1.カビによって強い・弱いはあるの?
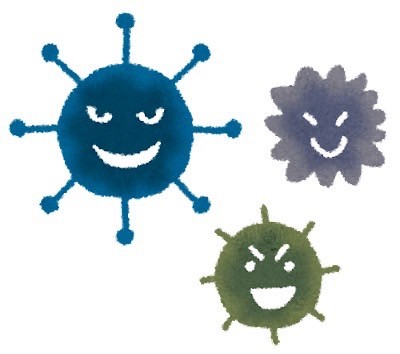
「強いカビってどれですか?」などと聞かれることがよくありますが、強さの定義によってそれは変わってきます。
ただ、恐らく大体の方は「強いカビ=除去しにくい」「弱いカビ=除去しやすい」という認識であることが多いと思います。
その認識でいうと、除去しにくいカビや比較的除去しやすいカビというものはあります。
そして黒カビは、除去しにくくて厄介なカビの1つでしょう。
そもそもカビの種類は、現在8万種以上あると言われています。
しかもこれは現在発見されているカビの数で、毎年増えています。
これだけ種類が多ければ、カビによって特徴が違うのも当たり前と言えるでしょう。
カビの種類を知ったら、まずはカビリスク診断
同じカビでも、住まいの湿気環境が強いと発生しやすく、再発もしやすくなります。
カビリスク診断でご自宅がどれくらいカビを招きやすい環境か、一度チェックしてみてください。
2.家庭に発生しやすいカビの種類と特徴とは
カビは様々な種類がありますが、似たようなカビが多く、パッと見ただけでは見分けがつかないものがたくさんあります。
そこでカビの知識がない人でも判断しやすいように、色別のカビの特徴を解説いたします。
2-1.黒カビの特徴

カビと聞いた時に、黒をイメージする方も多いと思います。
お風呂場やカーテン、エアコンなど家のいたるところで発生する黒カビはクラドスポリウムという種類のカビが中心となっており、実際は黒ではなく濃い緑色をしています。
他のカビ以上に強い生命力を持っており、一度発生すると除去が難しいのが特徴です。
また、除去できたように見えても根が残っていて、再発することが多いというのも厄介に感じるでしょう。
そして、人間にとって特に危険なカビとされるエクソフィアラも黒カビに含まれています。
室内に小さな斑点のようなカビを発見した場合、黒コウジカビ(アスペルギルス・ニガー)ということもあります。
黒カビは一度生えてしまうと、除去が難しいので、広範囲に渡っている場合や再発を繰り返している場合はカビ取りの専門業者に除去依頼した方が良いでしょう。

2-2.青カビの特徴

青カビは腐ったみかんやパンに生えることの多いカビです。
青カビといっても種類が様々で、ペニシリンの元となるなど有用なカビもありますし、ブルーチーズなど食べられるカビもあります。
しかし、肉眼では大丈夫なカビなのか判断はできないので、食品にカビが生えてしまったら食べないようにしましょう。
カビが生えた部分を取り除いたとしても見えないカビの胞子が付着している可能性が高いため、一部分だけ食べるというのもやめてください。
青カビは食品だけでなく、家具の裏や衣類などにも発生することがあります。
黒カビは奥まで根を張っているものですが、青カビは表面のカビなので黒カビより除去しやすいですが、黒カビよりも飛散しやすいので対処を間違えると一気に広がる恐れがあります。
そういう部分では厄介なカビと言えるでしょう。
2-3.白カビの特徴

白カビは食品や木材などの自然素材に発生しやすいカビです。
見た目が綿のようにふわふわとしていることから、埃と間違えることもあるでしょう。
木材に発生しやすいという特性から、押し入れやクローゼット、衣類などに生えることが多いカビです。
綿素材でも繁殖しやすいカビであるため、押し入れに収納した布団がいつの間にかカビだらけになっていた、という経験をされた方も少なくないはずです。
白カビも青カビと同じように飛散しやすいカビなので、カビを拡散させないように注意しましょう。
2-4.赤カビの特徴
畑などの土に生息し、作物に取り付いて繁殖することが多い赤カビです。
家の中ではごはんやパン、金属に生えます。
また、マイコトキシンという毒素を生成することもあり、これが人の体に入ると嘔吐や下痢といった症状を引き起こすこともあります。
ところで、赤カビと聞いた時「お風呂などで見られる赤い汚れ(ピンク汚れ)のこと?」と思う方も多いのではないでしょうか。
実はこちらは赤カビとは別物でルドトルラという酵母菌の一種で、そもそもカビではありません。
なお余談ですが、ルドトルラは人間の皮脂や石鹸カスを栄養にし、繁殖するスピードは黒カビの10倍とも言われています。
洗剤などでこすると落とせるのですが放置するとカビのエサとなるため、発見したらなるべく早めに除去しましょう。
3.カビの種類別の対処方法

では、ここからはカビが発生してしまった場合の対処方法をご紹介します。
色素が沈着し、素材の奥まで菌糸を伸ばしている場合、表面だけ除去しても再発する可能性があります。
また、カビを殺菌できたとしても、カビの色素が残ってしまうでしょう。
この場合は漂白効果のあるカビ取り剤を使用しなければなりません。
カビが生えた素材にも寄りますが、基本的には以下の手順でカビ取りをしましょう。
①消毒用エタノールや逆性せっけん、次亜塩素酸水などを使ってカビを殺菌する
②色素が残っている場合には漂白効果のあるカビ取り剤を使用して色素を漂白する
③それでも落ちない場合(素材の奥まで発生している)は業者へ相談する
お風呂やシンクなどすぐに流水で洗い流せる場所の場合は、①はやらずに②から実行しても構いません。
それでは、カビの種類別のカビ取り方法をみていきましょう。
3-1.黒カビの除去方法

黒カビは他のカビと違い、簡単に除去することができません。
除去にあたってはカビ取り剤のような強力な液剤を使って対処する必要があります。
ただし、塩素系漂白剤や塩素系カビ取り剤は毒性の強い水酸化ナトリウムなどの成分が含まれています。
付着すると皮膚が溶けてしまったり、酸性の洗剤と混ざると危険な塩素ガスが発生したりする恐れがあるため、取り扱いには十分注意しましょう。
塩素系カビ取り剤などを使う時は、必ず以下のことを守ってください。
- 換気する
- 他の洗剤と混ぜない
- マスク、ゴム手袋、ゴーグル、長袖の服を身に付けて体を保護する
基本的には、カビ取り剤は以下のような水回りで使用できます。
- お風呂
- 洗面所
- トイレ
- キッチン
水回りであれば、カビ取り後にしっかりと水で洗い流せるので、危険な成分を残さないようにすることができます。

ジョンソン カビキラー
出典:Amazon
■関連記事■カビ取り時に次亜塩素酸ナトリウムを使用する際の注意点
しかし、壁紙や天井など水で洗い流せない場所に黒カビが発生している場合もあるでしょう。
そのような時は、安全性の高いカビ取り剤を使用してください。

カビ取り業者のハーツクリーンが開発したカビ取りマイスターキットは、実際に業者が使用している液剤を誰でも使えるように改良した商品です。
そのため自宅でプロレベルのカビ取りができますし、危険な成分は含まれていないため壁紙のカビ取りにも使用できます。
もちろん水回りでも使用できるので、1つ持っていると便利でしょう。

カビ取りだけでなく、防カビも行いたいならカビ取りマイスターキットがおススメです。
こちらは防カビ剤もセットになっています。

もし自力では除去が難しい場所にカビが発生した場合や、広範囲に渡ってカビが発生している場合は、一度カビ取り業者に依頼してみてください。
■関連記事■【2026年版】カビ取り業者の選び方|失敗しない依頼ポイント&おすすめ業者比較

3-2.青カビの除去方法
青カビは、家具や壁などの表面に発生している程度であれば以下の液剤で除去することが可能です。
- 消毒用エタノール
- 次亜塩素酸水
- 逆性石けん(水で希釈)
除去方法は、消毒用エタノール(次亜塩素酸水、逆性石けん等)を布巾や刷毛などに染み込ませて、カビ部分に塗布し、数分経ってから布で除去していきます。

ドーバー パストリーゼ77
出典:Amazon

エスエーシーラボ ジアニスト
出典:Amazon

アリナミン製薬 オスバンS
出典:Amazon
衣類に発生した場合も消毒用エタノールで除去できますが、素材の繊維の奥深くまで菌糸を伸ばして色素沈着を起こしている場合には、漂白効果のある液剤を使用しましょう。
色柄ものに塩素系漂白剤を使用すると色落ちしてしまうため、酸素系漂白剤がおススメです。

グラフィコ オキシクリーン
出典:Amazon
壁紙などにびっしりと青カビが生えて自力での除去が難しい場合には、カビ取り業者に相談するのがいいでしょう。
またカビの状態によっては、壁紙の張り替えが必要なこともあります。
いずれにしても、自力での対処が難しい場合には早めに業者へご相談ください。

3-3.白カビの除去方法

白カビは、畳やフローリング、木材や布製品などに発生しやすいものです。
見た目が埃と似ているため掃除機で吸ってしまう方がいらっしゃいますが、そうすると排気口からカビの胞子をまき散らすことになり、悪化させてしまいます。
また、水拭きだけで済ませる方もいますが、これも一時的に見た目が綺麗になっているだけです。
すぐに再発しますし、むしろカビが好きな水分を与えているためカビの繁殖を促すでしょう。
白カビが発生した場合は、青カビと同じように消毒用エタノールや次亜塩素酸水、逆性石けんなどを使って除去しましょう。
他にも衣類なら以下の方法もあります。
- 酸素系漂白剤で除去する
- コインランドリーで乾燥させて熱で死滅させる
- クリーニング業者に依頼する
カビは少しでも残っていると再発しやすいため、大切な服や靴、バッグであればクリーニングとあわせてガス滅菌に依頼するのが一番でしょう。
3-4.赤カビの除去方法
赤カビは、酵母なのかカビなのか見分けにくい場合があるため、基本的には洗剤等を使って除去し、消毒用エタノールや次亜塩素酸水等を使って殺菌します。
金属に生えた場合は削り取るという方法もあります。
4.カビの発生を防ぐための対策

最後に、カビの発生を予防するためのポイントをご紹介します。
カビは以下の条件が揃っている場所に発生しやすいものです。
- 水分・湿度(60%以上)
- 温度(20~30℃)
- 栄養源(埃や食べカス、皮脂汚れなど)
- 酸素
これらのうち1つでも欠けているとカビが繁殖するのを抑制できるので、以下のカビ対策を積極的に行うようにしてください。
- 換気をこまめにおこなう
- ホコリや汚れを残さない
- 不用品は処分しモノをなるべく減らす
- 結露対策をする
- 湿度管理をする
- 空気清浄機を活用する
4-1. 換気をこまめにおこなう
換気は、室内の湿気や空気中の有害な物質を排出し、新鮮な外気を取り入れることができます。
また、室内の湿度を適切なレベルに保ち、カビの発生を防ぐ役割もあります。
換気の方法として、複数の窓を開けて部屋中の空気が循環するようにしてください。
また水回りなど、換気扇がある場所ではこまめに利用しましょう。
特に湿度が高い季節やシャワーや料理の後など、湿気が発生しやすいタイミングでの換気が効果的です。
4-2. ホコリや汚れを残さない

カビは繁殖するために、埃や汚れなどを栄養源にします。
また埃が蓄積しているとそこに湿気が含みやすくなり、カビの発生を促進する原因となります。
カビを防ぐためには、定期的に掃除機をかけたり、拭き掃除をしたりしましょう。
特に部屋の隅や家具の裏側、カーペットの下など、見落としがちな場所も重点的に行ってください。
清潔な環境を保つことができれば、カビの発生リスクを低減することができます。
4-3. 不用品は処分しモノをなるべく減らす
不用品や不必要なモノが多いと、その周りに空気が滞りやすくなり、湿気の原因となります。
不要な物は処分し、必要最低限のモノに整理することで、室内の通気性が向上し、湿気がこもりにくくなります。
■関連記事■モノが多い部屋はカビが危険!原因から対策までプロが徹底解説

4-4. 結露対策をする
湿度が高い時や、外と室内の温度差が大きい時は、窓や壁に結露が発生することがあります。
カビは濡れている場所を好むため、結露が発生している箇所はカビの発生リスクも高まります。
結露を防ぐためには、適切な断熱や通気を確保し、室内の温度と湿度を調整することが必要です。
窓の結露の場合は、結露防止シートを貼ることで防ぐことも可能です。
■関連記事■結露によるカビ発生を防ぐ方法とは?湿気対策の基本と予防策7選

ニトムズ 窓ガラス 結露防止シート
出典:Amazon
4-5. 湿度管理をする
湿度が高いとカビが繁殖しやすくなります。
湿度計を使用して室内の湿度を確認し、適切な範囲に保つよう心掛けましょう。
湿度が高い場合にはエアコンの除湿機能や除湿機を活用し、湿度を60%以下に保つように心がけてください。

タニタ 温湿度計
出典:Amazon
4-6. 空気清浄機を活用する
空気清浄機は空気中の埃や微粒子を取り除き、清潔な室内環境を維持するのに役立ちます。
こうすることで、部屋に埃などの汚れが溜まりにくくなります。
またカビの胞子も吸い取ってくれるので、カビも生えにくくなります。
最近は除菌効果のある空気清浄機も多いので、効果的なものを選んでみてください。
5.まとめ
今回はカビの種類別の特徴やカビ対策についてご紹介しました。
まずはカビが発生しないようにカビ対策を行いましょう。
室内に湿気がこもらないようにして、カビの栄養源になる汚れを取り除くことでカビのリスクを大幅に減らすことができます。
- 換気をこまめにおこなう
- ホコリや汚れを残さない
- 不用品は処分しモノをなるべく減らす
- 結露対策をする
- 湿度管理をする
- 空気清浄機を活用する
これらのことを意識して行っていたとしても、雨が長く続いたり、立地などの影響でカビが生えてしまうこともあるでしょう。
カビは放置するとあっという間に部屋中に広がり、健康被害を引き起こす原因にもなるため、早急に対処することが重要です。
初期段階であれば、カビ取り剤などを使用してご自身で除去することも可能です。
自力では難しいようでしたら、無理せずにカビ取り業者に依頼しましょう。







