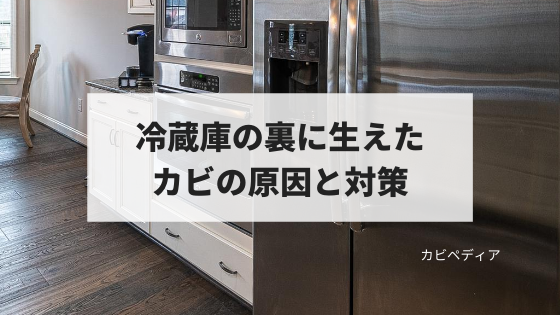
久しぶりに冷蔵庫を動かしたら、カビ臭さを感じたり、黒カビを見つけたことはありませんか?
冷蔵庫の裏は温度差による結露が起きやすく、さらに通気性が悪いため湿気がこもりやすい環境です。
あまり動かす機会もないためホコリが溜まりやすく、カビにとっての好条件が揃ってしまうのです。
カビは健康に悪影響を及ぼす可能性もありますし、食品が入っている冷蔵庫にカビが生えるのは、衛生的にも心配ですよね。

この記事では、冷蔵庫の裏にカビが生える原因と、冷蔵庫の裏・裏の壁に生えたカビ取り方法をそれぞれ解説します。
また、再発を防ぐために日々取り組める予防策もあわせてご紹介します。
普段なかなか目にしない場所だからこそ、この機会にお手入れをしてみてくださいね。
| この記事で分かること |
| ・冷蔵庫の裏にカビが生える原因 ・冷蔵庫の裏、裏の壁に生えたカビ取り方法 ・冷蔵庫裏のカビ予防策 |
目次
1-1.実は冷蔵庫の裏は、カビが好む環境
カビが発生する条件は、温度、湿度、栄養分の3つがそろったときです。
| カビの好む気温 | 20~30℃ |
| カビの好む湿度 | 60%以上 |
温度は20℃~30℃、湿度は60%以上、栄養分はホコリなどの汚れ等です。
日本では多くにご家庭が一年を通して室温は20℃~30℃程度に保たれていることが多く、日本の気候は湿度が高いため、カビが発生しやすい環境なのです。
冷蔵庫は壁に沿って置き、なかなか動かす機会がありませんよね。
1-2.ホコリも原因に

電化製品には静電気で引き寄せられ、ホコリが集まりやすいです。
特に冷蔵庫や電子レンジなどキッチンの電化製品には油とホコリが混ざり合い悪性のホコリになりがちです。
冷蔵庫の下、壁と冷蔵庫の間、冷蔵庫の天板にはホコリがたまりやすいです。
壁などにぴったりとつけて冷蔵庫を設置している場合には冷蔵庫の裏に空気が滞留しやすく、湿気を含んだ空気とたまったホコリを栄養分にしてカビが発生するのです。
冷蔵庫の裏にカビが生えると、そこに面している壁や床にもカビが生えてしまいます。
湿気やホコリが多い環境では、カビの繁殖スピードは速く、広範囲にカビが発生してしまいます。そのため、そうなる前に早期発見と対処をしていきましょう。
- 冷蔵庫の裏にカビが生える原因は油とホコリがカビの栄養源となるから
- また、家電製品は静電気によりホコリが蓄積しやすい
- 食品カスや手あか、水分などもカビの原因に
2.冷蔵庫の裏に生えたカビを取る方法
2-1.消毒用エタノールを使用する方法

用意するもの
- 消毒用エタノール
- ぞうきんまたはキッチンペーパー

ドーバー パストリーゼ77
出典:Amazon
①消毒用エタノールをぞうきんまたはキッチンペーパーにつけ、冷蔵庫の裏を拭きます。
②乾燥させて終了です。
軽度のカビであればこれだけでも十分取れるのですが、取れない場合にはその2へ
2-2.塩素系漂白剤を使用する方法

用意するもの
- 塩素系漂白剤
- ぞうきん 3枚
- ゴム手袋

ジョンソン カビキラー
出典:Amazon

花王 カビハイター
出典:Amazon
①ぞうきんに塩素系漂白剤をつけ、冷蔵庫の裏を拭きます。
②水で濡らしたぞうきんで塩素系漂白剤をしっかり拭き取ります。
③きれいなぞうきんで乾拭きし、扇風機やサーキュレーターを使用して乾かします。
※注意点※
- 必ず部屋の換気をしながら作業してください。
- 肌荒れの原因になることがありますので、ゴム手袋を着用してください。
- 大きな冷蔵庫など、塩素系漂白剤をたくさん使用する場合にはマスクやゴーグルも用意すると安全です。
3.冷蔵庫の裏の壁に生えたカビを取る方法
カビが生えているとカビキラーを使用したくなりますが、壁紙に使用するのは避けてください。
カビキラーなどの塩素系漂白剤を壁紙に使用すると、色落ちすることがあります。
真っ白い壁紙や壁なら問題ありませんが、色柄物や白い塗料などを使用している場合には注意が必要です。白い壁でカビキラーなどを使用する場合でも、壁の目立たない箇所で色落ちなどの問題がないか確認してから全体に使用するようにしましょう。
3-1.重曹と消毒用エタノールを使用する方法

用意するもの
- 重曹
- 消毒用エタノール
- 酸素系漂白剤
- ぞうきん2枚
- 容器

シャボン玉石けん 重曹
出典:Amazon

グラフィコ オキシクリーン
出典:Amazon
①重曹を容器に入れ、水を加えてペースト状にします。
②ペースト状になった重曹に酸素系漂白剤を加えて混ぜます。
③そうきんに消毒用エタノールをつけ、壁に液を染み込ませるようにしてカビを拭き取ります。
④消毒用エタノールが乾いたら②のペーストをカビが生えている箇所を覆うように塗ります。
⑤5分程度放置したらぞうきんで拭き取り、さらにぞうきんで乾拭きします。
この方法はカビが軽度の場合に有効です。カビがひどいときにはその2の方法を試してみてください。
■関連記事■実はカビだらけ!?冷蔵庫の効果的な掃除術とカビを防ぐコツ完全ガイド
3-2.壁や壁紙用のカビ除去スプレーを使用する方法

用意するもの
- 壁紙に使えるカビ取りスプレー
- ぞうきん
- ゴム手袋

純閃堂 カビ取り侍 液スプレー 標準タイプ
出典:Amazon
①カビが生えている箇所に表面が湿る程度まんべんなくカビ除去スプレーをします。
②15分程放置し、カビが残っている場合には再度スプレーし15分放置します。
③カビが消えたら、水拭きしてしっかりと乾燥させます。
注意点
- 必ず部屋の換気をしながら作業してください。
- 目立たない箇所で色落ちなどの問題がないか確認してから作業するようにしましょう。
- 広い範囲を作業する場合には、マスクやゴーグルも用意すると安全です。
- 扇風機やサーキュレーターを使用すると乾燥にかかる時間を短縮できます。
- カビがなかなか落ちない場合には、この工程を複数回くり返すことによってカビを落とすことができます。
3-3.カビ取り業者レベルの液剤を使って除去する

冷蔵庫の裏のカビは市販の液剤では落ちなかった場合、カビ取り業者レベルの液剤を使って除去するという方法も。カビ取りマイスターキットは、プロレベルの液剤を家庭用にパッケージ化したものです。
除カビ剤だけでなく防カビ剤もセットですので、同時にカビ予防したい方にもおすすめです。

4.冷蔵庫の裏のカビ予防方法

4-1.こまめにホコリを除去する
冷蔵庫の周りがホコリだらけだと熱伝導率が下がり、電気代が上がってしまうこともあります。
定期的に冷蔵庫を動かし、掃除機でホコリを吸い取り、こまめに掃除をしましょう。その際に床だけでなく、冷蔵庫本体の裏側にたまったホコリも掃除機で吸い取りましょう。冷蔵庫を動かすのが面倒という方は、ハンディモップを使用して冷蔵庫の周りのホコリを取り除くようにするのがおすすめです。
ホコリが固まって取れないときにはリビング用の洗剤(マイペット等)をかけるとぞうきんで拭き取りやすくなります。
また、冷蔵庫を置くときには壁にぴったりとくっつけずに10㎝程離して風の通り道を作りましょう。
壁から少し離して置くことで、湿気が滞留するのを防ぐことができます。
4-2.冷蔵庫の上のホコリは新聞紙やチラシでキャッチ
冷蔵庫の上の天板にはホコリがたまりやすいです。
でも、こまめな掃除は面倒だし背の高い冷蔵庫の上は見えないから掃除を忘れがちです。
そこで、新聞紙やチラシを天板の上に広げて敷くとホコリを勝手にキャッチしてくれるので、3か月に1回程度交換するだけで簡単にホコリを取り除けます。
新聞紙やチラシを交換するだけなので手も汚れませんし、ぞうきんで拭く手間もありません。
こまめな掃除が面倒な方や忙しくて掃除するヒマがない方などは今日から試してみてはいかがでしょうか?
4-3.カビ取り専門業者に依頼も検討しましょう。

冷蔵庫の裏のカビがなかなか取れなかったり、掃除してもすぐにカビが生えてくる場合などはカビ取り専門業者に依頼してみましょう。
カビ取り専門業者はカビ取りのプロですので、確かな知識と豊富な経験で場所や素材に合わせたカビ取りをしてくれます。
自力では難しいカビの根っこまで除去してくれますので、カビが再発するのを防ぐことができます。
相談や見積もりは無料の業者が多いですので、自分でカビ取り作業するのは不安な方や何度もカビが発生して困っているという方は一度相談してみるのがおすすめです。

まとめ
- 冷蔵庫の裏のカビは早期発見と対処が重要です。
- 冷蔵庫裏の湿気とホコリがカビが発生する原因になります。
- カビの程度で対処方法が異なります。
- こまめな掃除でホコリ除去と冷蔵庫を壁から離して置くことがカビ予防になります。
- カビ取り専門業者への依頼も検討を!
■関連記事■食器棚にカビが生える5つの原因とすぐできる除去法・再発防止策まとめ
■関連記事■キッチンのカビは重曹で予防できる?!ナチュラルクリーニングの専門家に聞いた簡単お掃除術①
<参考文献>
・主婦の友社『暮らしの裏ワザ便利帳Best500』2012年、主婦の友社
・主婦の友社『保存版一生モノの知恵袋』2018年、主婦の友社
・沢井竜太『おそうじの超ベストアイディア2020』2020年、晋遊舎









コメント